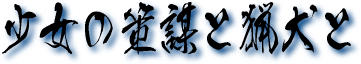 ※性的表現が含まれますので、苦手な方はこちらからお戻りください。 暑さで目が覚めた。 盛夏を謳歌するアブラゼミの大合唱が不快レベルを上昇させる。暑い。寝汗で濡れそぼった肌着を脱ぎ捨てつつ、私は寝床から身を起こした。 丸い明かり取りの窓から差し込む日差しで、地下部屋は薄暗く照らされている。私は立ち上がると、日課となった部屋の点検を始めた。天井と壁の交わる場所、床と壁の交わる場所、壁同士が交わる場所。丹念に一分の隙も漏らすまいと目を凝らす。 石膏によって塗り込められた“ 私は不動産業の傍ら古物商を営んでいる。万座区の開発によって時ならぬ活況を見せている不動産業だけでも十二分にやっていけたが、死んだ親から受け継いだ土地の売り買いよりも、ほとんど利益を生まない趣味のような古物売買に、より力を注いでいた。由来だけは御大層なガラクタを集めることに、自虐的な愉しみを覚える毎日であった。
あの男―― それから後も鵺木は私の元に“貴重品”を持ち込んでは、金をせびって行った。「神封じの銅鏡」や「鬼の手のミイラ」といった明らかなまがい物ばかりであったが、私が大げさに喜んでみせると鵺木は調子に乗って、持ち込む物品のインチキ臭さを際限なくエスカレートさせて行った。 ある日、単なるガラス玉との引き換えに四百万円を要求してきた鵺木に向かって、私は柔和な笑みを浮かべながらこう言ってやった。 そろそろ一つくらい本物の貴重品が欲しいのですが、と。 それまで得意満面で薀蓄を並べ立てていた鵺木の顔が一瞬で蒼白になる様は傑作だった。大量の汗をかき、目を泳がせ、そわそわと居心地悪そうに腰の位置を変えて、すぐにでも逃げ出したそうにしていた、あのペテン師の顔! 時価四百万円のガラス玉を床に叩きつけ、靴底で踏み砕いてやると、鵺木は土下座して許しを請うた。 待ちに待ったこの逆転の時のために用意しておいた事実を突きつけ、私は鵺木に取引を持ちかけた。鵺木の「大倉庫」に眠る貴重品と引き換えに今までの詐欺行為は水に流そう、と。その申し出に顔を引き攣らせて「少し時間が欲しい」と言った鵺木だったが、既に結果は見えていた。果たして、二日後には承諾の電話が鵺木からかかってきた。 石膏の剥離は見当たらなかった。少しだけ安堵してテーブルの前に座り込む。慎重に“角”を落とした丸いテーブルの上には、折り目がつかないように細心の注意を払って取り扱われている書物が三冊置いてある。 『ネクロノミコン(ディー版)』。 『妖蛆の秘密』。 『ナコト写本』。 三冊どれを取っても隠秘学の稀覯書中の稀覯書だ。ディー版の『ネクロノミコン』と『妖蛆の秘密』は数年前に法外な金額を対価として入手したもので、『ナコト写本』は数日前にデュッセルドルフから空輸されてきた。鵺木佑一の手配によって。 禁断の呪法を伝えるこれらの書物から危険な知識を汲み出さなければならないほどに危機的な状況に陥ってしまったのには、次のような訳がある。 それは多面体の水晶のようだった。
鵺木佑一が、自ら管理する「大倉庫」から持ち出してきた本物の“貴重品”。首が回らないほどの借金により私からの援助なしには日常生活すらままならない鵺木は、体面を省みることなく先祖の残した財産に手をつけた。そうして持ち出されたのが、その多面体であった。 捧げ持つ多面体が転ばないように底面が平らに均されただけの石の台座が付いていたが、それは装飾品としてではなく機能のみを重視して作られた無造作なものだった。その上に乗っている透き通った球形の鉱石は無計画に面取りされて、まるで出来の悪いゴルフボールのように見えた。実際の大きさもゴルフボールほどではあるが、少し楕円球がかっている。 いつものインチキ商品を売り込む時とは打って変わって、鵺木は潜めた小声でその多面体について語った。これは過去視の出来る水晶なのだ、と。それが真実であれば多面体を三千万円で買い取ると約束すると、鵺木は歪んだ笑みのような表情を浮かべ、この場で実験してみせようと言ったのだった。 鵺木の携えてきた香木を香炉で焚き、精神を鋭敏化させる効果のある香煙を充満させた事務所の一室で、その実験を行った。香煙を吸った私と鵺木は半ば朦朧としながらも一心に多面体の中を見つめ続けた。もしこれもインチキであったなら、人を雇って鵺木を痛めつけてやる事を考えていた私であったが、多面体を見つめているはずの自分の意識・精神が“時間を遡っていることに気付いて”、これがインチキではないことを理解した。――ああ、インチキであってくれたなら!! 無数の国家や種族の興亡を見届けた後、私と鵺木の精神は数十億年前まで時を遡った。見える光景はただ混沌であり、目に嬉しい類のものではなかったが、得られた満足感、達成感は肉無き魂が震えるほどであった。 意思なくたゆたう混沌を眺めていた私が、遠くに極小さな歪みを見つけたのが、恐怖の始まりだった。怠惰な混沌の身じろぎとは別種の、何らかの意思・知性を感じさせる歪みを見つけ出してしまったのだ。私たちではない他の人間、いや、人間ですらないかもしれないナニかが、原初混沌の地球を訪れている場面に出くわしたのかもしれない! 混沌の中で強い光を放つかのように、私は歓喜に震えた。それが歪みの注意を引いてしまった。 鵺木の発した警告の声――注意を喚起する色を持った意思――は、しかし、遅きに失した。遠くに見えていた歪みが瞬きする間に私の眼前に迫り、裂けた口の端をまるで邪悪な笑みのような形に吊り上げて見せたのだ! 青白くぶるぶると震える膿汁に覆われたその痩せた身体は何らかの獣を思わせ、私を引き倒そうと伸ばされた緑膚の前足には爪があった。赤く燃える双眸には明らかな邪悪さと嘲りが溢れ、牙のある口から出た尖った舌は恐怖に囚われた私の心を余さず啜り尽くさんとして目一杯伸ばされていた。“そいつ”が発散していたのは紛れもなく純粋な、飢えと渇き、だった。 私は恐慌に陥り、悲鳴を上げた。迫り来る爪と舌から逃れようにも、私の精神は、その場から微塵も動けなかったのだから! 意識が途切れ、私は死を間近に知覚した。 ……意識を取り戻すと、私は床の上にだらしなく横たわっていた。汗、涙、鼻水、涎でべとついた顔を上げると、窓を開けて香煙を散らしている鵺木の姿が見えた。そこは、元の事務所の一室だった。私が意識を取り戻したことに気付くと、鵺木は土下座して詫びた。何やら必死で弁解していたようではあったが、私の耳にそれは入ってこなかった。土下座したまま弁明する鵺木を、私は力の限りに蹴り飛ばした。鼻血を流し、嘔吐しながら転げ回る鵺木を容赦なく何度も足蹴にした。鵺木が意識を失って動かなくなった後、暴行に疲れ果てて床に座り込んだ私は、この時になってようやく、自分が失禁していた事に気付いたのだった。 隣室にある業務用の大型クーラーで、この地下部屋には冷風が送り込まれているはずだ。しかし、白凰市が連日記録的な猛暑に見舞われているのに加え、風通しの悪い地下に作られたこの部屋には熱が篭り易く、薄暗さと閉塞感もあいまって不快指数を上げるばかりであった。 タオルで汗を拭うと、テーブルの上にある三冊の魔道書の内の一冊、『ナコト写本』に手を伸ばす。ウォズリングの研究書にあった引用箇所が見つかれば、その前後に出し抜く方法が記されているかもしれない。奴を――ティンダロスの猟犬を。 混沌の中で出くわした青白い膿汁滴るの生き物の正体はすぐに判明した。
『ネクロノミコン』や『妖蛆の秘密』で仄めかされる時空を越えて追ってくる腐肉喰らい。時間の“角”に沿って生き、“角”を通じて現れる異次元の怪物。狙った獲物を執拗に追跡してその魂を貪欲に貪る飢え渇いたもの。 それは古来より「ティンダロスの猟犬」と呼ばれ、恐れられている存在であった。 鵺木の機転によって時間の“曲面”に沿って現代に戻り、奴らの最初の襲撃からは辛くも生き延びた私は、飢餓によって駆り立てられた奴らが一度目をつけた獲物を簡単には諦めたりしない事を知った。奴らは何十億年もの時を“角”から“角”へと跳躍し、やがて獲物のいる時空へと辿り着いて、その魂を喰らい尽くすのだ。その追跡から逃れることは至難とされる。 しかし、思う。私は過去に死んでいった被害者たちとは決定的に違うのだと。私には『ネクロノミコン』や『妖蛆の秘密』から得た奴らに関する知識があり、対抗手段を講じる財力があり、手足となって働く使用人がいた。使用人とはつまり、鵺木佑一の事だ。 私はまず建築業者を手配し、所有する別荘の地下室に球形に近い四畳ほどの部屋を作らせた。概ね木板の貼り合せで作られたその部屋の外観は、まるで遊園地にあるアトラクションの一種のようにも見えた。次に左官屋を呼んで、部屋内部の“角”という“角”を全て石膏で塗り込めさせた。建築業者も左官屋も怪訝な表情を浮かべて作業に当たったが、私に十分な報酬を支払う用意がある事が分かると、手抜かりなくそれぞれの作業を終わらせた。歪ながらも球の内部のように滑らかに“角”を無くした部屋が、こうして完成した。“角”の無い部屋に閉じ篭った私を奴が諦めるか、それとも閉じ篭っていることに耐え切れなくなった私が部屋から飛び出して奴に喰われるか。命がけの我慢比べだ。 偏執的なまでの慎重さで選抜した必要最低限の品を“角”の無い部屋に運び込み、私はティンダロスの猟犬との戦いを始めた。電気機器は何一つ持ち込んでいない。機械内部に“角”を持つ部品が使われているからだ。丸い明り取りの窓から差し込む陽光と月光だけが部屋を照らす照明であり、隣室からダクトを通じて冷風を吹き入れている業務用クーラーがこの夏を乗り切るための冷房器具だった。 ティンダロスの猟犬が「匂い」を辿って私の前に現れるまでには半月以上の時間があるので、鵺木に命じてその対抗策を探させている。金に糸目はつけなかった。数日前に手元に届いた『ナコト写本』は世界中の秘術探求者たちにとって垂涎の一冊だ。鵺木はこれをデュッセルドルフの古書収集家から買い取って私に送った後、ケルンに赴いて次なる算段を取り付けるとの事だった。私への罪悪感からか、それとも今回の事件が外に漏れることを危惧してか、鵺木は精力的に働いている。この事件の解決なくしては、社会的にも金銭的にも鵺木に破滅が訪れるのは間違いない事なのだから。 「――お食事です」 『ナコト写本』の字面を苛々と追っていた私に、部屋の外から声がかけられた。時計の類は持ち込んでいないので正確な時間は分からないが、おそらく今が朝の8時ちょうどなのだろう。朝食は8時に持ってくるように言いつけてある。人里離れたこの別荘で、地下部屋から一歩も出ることの出来ない私の身の回りの世話をするためにやってきた少女に。 入念に“角”の落とされた扉を薄く開けると、そこに薄青色の和服姿の少女が盆の上に朝餉を乗せて佇んでいた。 少女の名は 私がこの地下部屋に閉じ篭るに当たって、誰か一人、身の回りの世話をさせる使用人が必要となった。秘密が守れて、しかも絶対逃げ出さない使用人が。
独身である私に残念ながらそのような伴侶はいない。金を積めばこの人里離れた別荘でひと夏を過ごしてくれる人間も見つかるだろうが、問題はその後だ。奇妙な部屋に閉じこもった男に食事を作り続けるという体験は、決して一人の胸の内に収めておける愉快な思い出とはならないだろう。そこから流布する風説を、私も鵺木も恐れた。しかし、意外な所から理想的な人物が浮かび上がった。私や鵺木と利害関係があり、前述した条件に合致する人物。それが鵺木の娘、言葉だった。 鵺木がドイツに発ってから数日後、私が地下部屋に篭る前日に、言葉は別荘にやってきた。真夏の日差しを眩しく照り返す白色の鍔広帽とノースリーブのワンピースを身に着け、最低限の荷物を詰めた小さな旅行鞄を持って、言葉は別荘の玄関に立っていた。艶やかな黒髪は肩で切り揃えられ、私に向かって深々とお辞儀をした時にはサラサラと彼女の耳元を流れた。初対面の男に会ったというのに物怖じした様子はまるでなく、この猛暑の中汗一つかいていないかのように凛として私を見つめていた。両の瞳は吸い込まれるほどに澄んでいたが、同時に底知れない深みに通じる黒々とした澱みにも見えた。卑屈でいけ好かない父親の面差しには、幸い似ていなかった。美人になるだろう――数年後には。 私の与える指示に、言葉は何一つ質問を挟まなかった。父親から事情を聞いているのか、それとも事情を聞かないように言い付けられているのか。僅かな戸惑いすら見せず、言葉は私の言いつける事に諾々と頷いていった。 毎朝決まった時間に冷房のスイッチを入れ、毎晩決まった時間に冷房のスイッチを切ること。三食の食事を用意し、決まった時間に地下部屋へ届けること。着衣は下着に至るまで全てこちらで用意したものを使用すること。絶対に“角”のあるものを地下部屋に持ち込まないこと、等々。 言葉は違える事なく指示をこなした。用意した着物は全て和服だったが、着付けを心得ているのか、隙無くそれを着込んで食事を運んできた。さすがに食事のレパートリーは少なかったが、それでも十分食せる味ではあった。途中、ドイツから鵺木が送ってきた『ナコト写本』を届けた時以外は、まるでビデオのシーンを繰り返し再生しているかのように、寸分違わぬ様子で食事を運び、空の器を下げていった。 朝餉を告げる声に応えて薄く開けた扉の隙間から顔を覗かせると、言葉はいつもの通りに深く腰を折った。狭苦しい地下部屋に押し込められた私が半裸で汗だくなのにもかかわらず、扉の外に立つ言葉は着物を着込みながらも汗一つかいていないように見えた。地下部屋に篭ってから半月、私のストレスは頂点に達していたのだと思う。私のために食事の用意をしてきてくれた少女の可憐さを滅茶苦茶に壊し、踏み躙ってやりたいと、そう思ってしまったのだ。 私は勢い良く扉を開けると、食事の乗った盆を捧げ持つ言葉の細い手首を掴んで部屋の中に引きずり入れた。当然盆は覆り、食器が音を立てて砕け散ったが、そんな事は気にもならなかった。 引きずり込んだ勢いのまま、言葉を仰向けに組み伏せる。言葉は何が起こったか分からないという風に少し目を見開き、私を見返した。悲鳴を上げようとしないその態度が、私の燃え盛る獣性に油を注いだ。襟元の合わせ目に両手を突き入れ、乱暴に左右に広げる。 「あ……やっ」 素肌をあらわにされた言葉は小さく怯えた声を上げ、手足をばたつかせて抵抗を始めた。しかしそれは男の縛めを振りほどくにはあまりにも弱々しかった。色白だと思っていた言葉の素肌は、胸元から腰にかけてが尚白く浮かび上がっていた。仄白い水着の跡――洒落たデザインのものではない、おそらくは彼女の通う学校の指定水着によって授業中にでも付いたのであろう跡――がついた胸元を、一筋の汗が流れ落ちる。常に凛とした態度を崩さない言葉が見せた焦りと怯えが、私を一層凶暴に興奮させた。飾りの無い下着を剥ぎ取ると、膨らみ始めた乳房とその頂点にある色づいていない漿果のような乳首、くびれきっていない腰周りが私の目を釘付けにした。 「や……ぁっ」 半裸に剥かれた言葉はもう一度だけ大きく抵抗して見せたが、それも私の縛めを解くには弱々しすぎた。抵抗は次第に小さくなり、やがて疲れ果てたのか、言葉は荒い息を吐きながら身体を弛緩させ、私から顔を背けるようにして横を向いた。抵抗が無くなったことを確認すると、私は言葉の解けかけた帯を彼女の臍の上辺りまで引き上げて邪魔にならないようにし、そして―― 純潔を散らせた瞬間も、言葉は泣き喚きはしなかった。 その後も逃げ出す事なく、言葉は決められた通りに仕事を遂行していった。食事を持ってくる度に性の相手をさせたが、抵抗は初めての時の一度きりで、以後は唯々諾々と私のなすがままにされた。行為の後、汗や体液でしとどに濡れた身体を清め終わると、まるで人形のように無表情な顔つきで、着物を手に部屋を出て行くのだった。
ここへ遣された時から、言葉にはその覚悟があったのかもしれない。最初から性的な奉仕も織り込み済みだったのだ。少しでも私の機嫌を取るために、純潔蹂躙も予想した上で、鵺木が娘を差し出したのだろう。真に唾棄すべき男だ、鵺木は。この憤懣が、全て娘に向けられる事さえも承知の上なのだ。 それから数日後、ケルンにいる鵺木から連絡が入った。紹介された古物収集家から、武器となりそうな魔術的な品を手に入れたとの報せだった。「 月明かりで目を覚ました。
夕食時にいつも通り言葉を抱いたが、既にその姿は無い。テーブルの上に並べられていた食器も片付けられており、どうやら私が少しまどろんでいる間に地下部屋を辞したようだった。身を起こしてテーブルの前に胡坐をかくと、傍らに置かれていた言葉が用意したと思しき真新しいタオルを手にとって、汗みどろの身体を拭き清める。たちまち汗と体液でタオルは汚れ、私は顔をしかめてそれを部屋の隅へと放り遣った。投げられたタオルによって、地下部屋の澱んだ空気が掻き乱され、肌にまとわりつく様などんよりとした熱が私の顔を撫でていく。 ……? 鼻が、悪臭をとらえた。私や言葉の体液の臭いではない。地下部屋に篭ってから二十日余り、ついぞ嗅いだ事の無い吐き気を催すほどの強烈な悪臭だった。五感を総動員してその発生源を探す。その内にも、悪臭は耐え難いほどに強くなってきている。  ヒタ…… ヒタ……むき出しのふくらはぎに押し付けられた感触に、私は思わず女のような悲鳴を上げてしまった。何か湿ったモノが、テーブルの前に胡坐をかいていた私の左ふくらはぎに触れたのだ。テーブルの下を覗き込もうと背を曲げた瞬間、今度はふくらはぎを襲った激痛に、私は引き攣ったような悲鳴を上げた。痛みに飛び上がらんばかりの勢いで後退ろうとしたが、テーブルの下にいる“そいつ”のせいで、それは許されなかった。 緑色の皮膚をした無毛の犬――“そいつ”がそこにいた。皮膚からジクジクと染み出す青白い膿汁と耐え難い悪臭を纏って、テーブルの下のあり得ない角度からその姿を現した“そいつ”が、尖った舌を嘲るかのようにチロチロと伸縮させ、耳元まで裂けた口で私の左足のふくらはぎから先を喰いちぎっていたのだった。 私は反射的に飛び退こうとしたが、左足首を失っていたためにバランスを崩し、テーブルから僅かに離れた場所に無様に倒れ込んだ。横向きに倒れた私の視線はテーブルの下を通り、部屋からの唯一の出入口までを見通す格好になった。その視線上にある二つの事実が、私に全てを理解させた。 テーブルの下は悪臭と黒煙が渦巻いており、その黒煙を割ってティンダロスの猟犬が実体化していた。私の身体から流れ出る血の一滴すらも余さずに舐め貪ろうとするその怪物は、二つ折りにされた小さな紙片の“角”を通って具現化していた。 そしてその先、開け放たれた出入口の扉のすぐ向こうに、半裸のまま膝を抱えた姿勢で私を見つめている言葉がいた。笑みすら浮かべる事なく、いつも通りの凛とした表情の彼女を見て、誰が怪物を呼び込む紙片を部屋の中に持ち込んだのかを、私は悟ったのだった。 (了) illust:脳痛男(ティンダロスの猟犬) |
