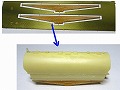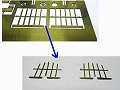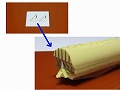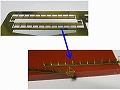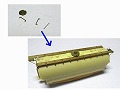|
タツヤ模型 ホキ1000
小野田セメント仕様です。今は会社名が変わってます。
|
 |
他に必要なのは0.3mm真鍮線が少し。
|
 |
説明書はA4両面印刷で3枚、6ページ。
補充部品の請求方法やら注意書きなど、結構細かいです。
エッチングパーツを最初に切り離すように書かれていますが、その都度切り離します。
|
 |
床板は3枚のプラ版を重ね合わせて接着します。プラ用接着剤です。
真鍮エッチングのように、不必要部分が付いたままです。
切削痕が結構あり、細かいクズがまとわりついています。
|
 |
このまま位置に気を付けて接着してから不必要部分を切断します。
今回はマイターボックスを使って切断しました。
|
 |
センターピンを接着する部分に穴が開いているので、入ることを確認します。
両方とも穴に入らなかったのでヤスリ掛けしました。
|
 |
一番上のプラ版に穴が開いているので、手すり用の穴を貫通させます。
0.5㎜のドリル歯でピンバイスを使いました。
床板の合わせがズレていると真っ直ぐ開かないかもしれません。
|
 |
手すりを切り出します。
思ったよりヤワヤワでした。すぐ曲がってしまいます。
|
 |
手すりを床板に固定します。ブレーキハンドルは片側だけです。
5箇所同時に穴に入れるのは難儀しました。
ここでセンターピンも固定しました。ゼリー状瞬着です。
|
 |
ホッパー本体は分割されたレジンキャストです。
バリを取りのぞいておきます。
|
 |
エポキシ接着剤で固定しました。
両側に付く三角形の補強部は位置のガイドが無い為、位置決めが難しいです。
|
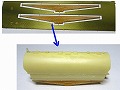 |
ホッパー下部に付く板を切り出して接着。
|
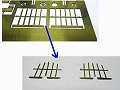 |
ホッパー妻板のリブを切り出します。
中央下部は三角に切り除いておきます。
|
 |
リブを妻板に沿わせて曲げます。
いいところで接着しますが、結構めんどくさいです。
|
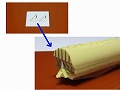 |
三角形のプラ板部品を三角形補強部に接着します。
|
 |
補助リブを切り出して、ホッパー妻板部へ接着します。
|
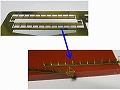 |
ホッパー上部に付くステップを切り出し、足を曲げておきます。
さらに端っこに補強枠(三角形)を接着します。
|
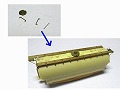 |
ハッチは分かりづらかったです。
真ん中の穴に0.3㎜真鍮線を入れ、両脇からパーツで挟み真鍮線の上からハンドルを固定。
ここだけハンダ付けすればよかったかも。
|
 |
ホッパー下部に車票を接着。
|
 |
床板とホッパーを固定します。
床板の細い部分がホッパーの下部にはまるようになっています。
ホッパー両脇の三角形の補強部がストッパーになり、位置が決まります。
|
 |
ハシゴと補強ステーを接着します。
接着する部品はこれで終わりです。
|
 |
いつものように洗浄、乾燥。
|
 |
忘れないうちに台車の組立。
加工するところはないです。
|
 |
乾燥したら塗装に移ります。
|
 |
クレオスの「Mr.プライマー・サーフェイサー1000」というのを使ってみました。
|
 |
実車を見たことがないのでネット上の写真を参考に色を調合してみましたが正解がわかりません。
ちょっと青みがかった灰色に近い白、をイメージしたのですが。
塗装時に埃が舞っていたようで、乾いたらプチプチと跡が残ってました。
|
 |
デカールが入っていました。
年数が経っているので使えるか微妙です。
|
 |
使う部分だけを切り離して水につけます。
台紙が丸まって焦りましたが、何とか車体に付けることができました。
|
 |
車体両側に転写したら乾燥を待ちます。
乾燥したら、はみ出した部分をカッターで切断します。
その後、半艶のトップコートを吹き付けておきました。
|
 |
台車を固定。
タッピングビスをセンターピンに差し込みます。
結構きついので、センターピンが剥がれ落ちる可能性があります。
|
 |
完成です。
前から見ても傾いてはいませんでした。
センターピンを固定する際に斜めになっていると車体が傾くので注意です。
|
 タツヤ模型 「ホキ1000」 作ってみた
タツヤ模型 「ホキ1000」 作ってみた