![]()
 テイクオフ TKF−2924 |
フェルナンド・ヒメーネス“わが心のサンポーニャ” 知る人ぞ知るボリビアの“黄金のサンポーニャ”、フェルナンド・ヒメーネス。彼は1982年に半音演奏をはじめて可能にしたクロマティック・サンポーニャの開発者であり、この楽器の現代最高の奏者である。本作はその彼のいわば自分史的なアルバムで、母国を代表する音楽家たちの作品16曲と自作4曲が收録されている。なかでも彼に半音管サンポーニャの開発をうながした巨匠エルネスト・カブールの代表作「緑の大木」や彼のチャランゴでヒットし日本でもおなじみの「きみの影になりたい」、そして定番「コンドルは飛んでいく」などが嬉しい聞ききものである。このところフォルクローレの好盤がなかっただけに、この1枚はファンの渇望をいやすことになるだろう。 |
 テイクオフ (TKF-2505) |
ジョニー・アルビーノ タンゴを唄う ジョニ−・アルビ−ノと言えば、全盛期のトリオ・ロス・パンチョスのトップ・ボイスとして度々来日し、日本ではいまなお絶大な人気を誇っている存在。本作はその彼がパンチョス脱退後に設立したスターブライト社に残したアルバムで、昨年10月末に本人から聴いたところでは74年にアルゼンチンで録音したものだという。日本での発売はこれまでなく、輸入盤で若干の人が持っている程度だったが、本作は数あるアルビーノのアルバムのなかでもベスト3に入る1枚である。それではと、先方とかけあってやっとCD化が実現したのだが、途中いろいろあっただけに感無量である。いま84歳のアルビーノ翁だが、録音時は56歳で、声も若々しく、アルビーノ節で聴かせるタンゴの名曲の数々はまさに絶品。なかで不貞を働いた母が父に殺されたことも知らずに贈り物を待っている子供を描いた「レジェスの夜」は涙もの。超お勧めの1枚。 |
 Argentin DBN Argentin DBN(CD51728) |
Jairo "Che Diario del Regreso" おそらく軍政下の母国にいづらくなっためと思うが、長年の不自由なパリ生活を経て、またその間アタウアルパ・ユパンキとの交流もあって、ハイロは素晴らしい歌手に成長した。そのことを実感したのは"Atahualpa por Jairo en vivo"を数年前に聴いたときだった。この最新作も期待を裏切らない充実した内容である。ゲリラ活動を展開していたボリビアで政府軍に捕まり、チェ・ゲバラが67年10月9日に処刑されたのは事実だが、遺体が飛行場の滑走路の下に埋められていたことが97年6月に判明。やがて掘り起こされた遺骨はボリビアからキューバのサンタ・クララに移送され、以前からあった腕の骨とともに埋葬されたのである。「ボリビアで」「飛行」「ハバナで」「サンタ・クララで」と題された章からなる本作『帰還への日々』は、同じアルゼンチンに生まれたハイロがチェに捧げたオマージュで、聴いていて胸が熱くなってくる。 |
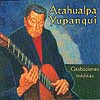 テイクオフ (TKF-2841) |
アタウアルパ・ユパンキ“未発表録音集” 朝日新聞の「今月の10枚」欄で、青木啓氏が珍盤と書いておられたが、たしかに「真室川音頭」が飛び出した時にはぼくも仰天した。1962年〜66年にかけて録音されたもので、その間の64年にユパンキは初来日を果たし、「千本松原」と「さらば日本」の2曲で日本の民謡をバックに日本の印象や民話や伝説を語りで紹介しているという次第。むろん、われわれには興味つきないトラックだが、それ以上に54〜58歳のドン・アタの精気に満ちた演唱やはりがすばらしい。偉大なパジャド−ル、ルイス・アコスタ・ガルシーアへのオマージュを語るミロンガの「南の歌い手」や雪の降る浜松で故郷の木に思いを馳せて作った「郷愁の老木」、気迫に満ちた「サンティアゴのチャカレーラ」などがとくに印象に残る。20歳当時のユパンキの写真にも感銘を受ける。なお、ラストの「バルガスのサンバ」が原盤では「風のサンバ」と表示されているのはちょっといただけない。 |
 (ES-0001) 問:03-3200-8984 本間一明&エスメラルダ |
本間一明“ラ・ディスタンシア” 名前はかねがね知っていたが、ここに来てCDとステージで本間一明の唄をじっくりと聴く機会があって、ぼくはすっかり彼のファンになってしまった。透明感のある深いバリトン・ボイスそのものが素晴らしく魅力的だし、歌唱に気品が漂うのもいい。スタートはわが母校でもある“都の西北”のサークルでトリオ・ロス・パンチョスのスタイルでラテンを唄い始めた時だというが、いまはパンチョスよりもむしろフリオ・イグレシアスを彷佛とさせるスタイルである。とはいえ彼の名誉のために特筆しておくが、フリオと違って2〜3曲聴くと鼻につくといったようなことはなく、聞き流すこともさせないぞという気迫というかひたむきさが彼の歌唱に秘められている。1980年から10年間有馬徹&ノ−チェ・クバーナの専属歌手として活躍した時代にもちろん聴いてはいたが、歌手としてはいまのほうがずっといい。ラジオでもかけた「ラ・ディスタンシア」が聴かせるが、映画『マンボ・キングス』の主題歌「我が心のマリア」もよく、「ナタリー」もぼくは本家のフリオのそれより気に入っている。ぜひ一聴をお勧めしたい。 |
DVD ソニ−・ミュ−ジック (SSBW8004) |
DVD“カジェ54” ラテンとジャズ双方のファンから省みられないなどと揶揄されたりするラテン・ジャズだが、どちらのファンも本作を見ればその魅力にとりつかれることだろう。32年前の1960年にスウエーデンに楽団を率いて行き、そこで現地の女性と恋に落ちてキューバに帰らなかったベボ・バルデス。つまり父に捨てられたことになるチューチョ・バルデスは95年頃にいまは米国に住む父と再会。またこの映画のために5年ぶりに2000年に会う。抱擁を交わした直後、父に「おまえ太ったな、まるでガマガエルみたいだ!」と言われて一瞬唖然とするが、チューチョはガハガハと笑い飛ばす。その後、父子は「ラ・コンパルサ」をピアノで連弾するのだが、その時の両者の表情がなんとも素晴らしい。これだけでも一見の価値ありである。ほかにパキート・デ・リベーラ、ジェリー・ゴンサレス、ミッシェル・カミーロ、ティト・プエンテらがフィーチュアされているが、ベボとカチャオのドゥオ、チコ・オファリル指揮の「アフロ・キューバン・ジャズ組曲」など見ごたえがある。ラテン・ジャズのなんたるかを伝えてあまりある傑作映画である。 |
 Concord Records Concord Records(CCD-2136-2) |
“Eddie Palmieri/La perfecta ˘” 「独りわが道をがむしゃらに行く」といった感じのあるサルサのピアニスト、エディー・パルミエーリ。その彼の2002年の新作は最近聴いたサルサでは出色の1枚で、久々に聴きごたえがある。La Perfectaと言えば、彼が1961年に結成したバンドの名前にして、62年に発表したデビュ−作のアルバム名でもある。40年ぶりに“第˘集”と銘打った意図はわからないが、ここに聴けるサウンドは当時の回顧でも郷愁でもなく、といって昨今のサルサ界にもの申すとか問題提起するといったことでもない。なにぶん全力疾走でワン&オンリーのサウンド世界を追求してきたエディーが、一息入れるといった感じか、軽い気持ちで作ったデビュー40年記念アルバムといったところかも知れない。ともあれ、むつかしいことを抜きにして楽しめることは確かだ。 |
 テイクオフ (TKF-ESPECIAL-6) |
“クリスティーナ三田エン・メヒコ/空に近い国” 2001年10月29日、ジョニー・アルビーノ翁が率いるパンチョスを聴きに行き、ゲストでクリスティーナ三田が唄った「羊飼い」と「麗しのハリスコ」の2曲を聴いて、こんなすごい歌手が日本にもいたのかと驚いた。ウアパンゴやランチェ−ラを得意とする彼女をメキシコに誘って本場の楽団で録音してみたい。ぼくのそんな夢がかなったのが今年6月のことで、14人編成のマリアッチ・オロ・フベニールの伴奏で「羊飼い」や「セミの歌」「ククルククー・パローマ」など5曲、第1級のトリオとして幅広く活躍しているロス・モラーレスのサポートで彼女のためのオリジナル曲である「空に近い国」や「ジャ・ラ・パガラス」「トゥス・オホス」など5曲、さらにキューバの大歌手エレーナ・ブルケの伴奏ギタリストとして95年に来日したフェリーペ・バルデスとのコラボレーションで「マリーア・エレーナ」など2曲を録音した。自画自賛になるが、彼女の魅力をとらえつくした画期的な1枚と自負している。ぜひご一聴のほどを! |
 テイクオフ (PQ-003) |
“ニコラス・カバジェ−ロの音世界〜タンゴ” アルパは中南米諸国に流布しているが、パラグアイではアルパが国民的な楽器ともなっているだけに、古くはフェリクス・ペレス・カルドーソやディグノ・ガルシアといった多くの名手を輩出してきたし、いまもそのことに変りはない。最近ではセサル・カタルド、マルセーロ・ロハスといった日本ではなじみのなかった人たちの演奏にふれてパラグアイのアルパ奏者の層の厚さに驚いたものだが、この度ニコラス・カバジェロの演奏を聴いて、この人こそ当代最高のアルティスタと確信した。パラグアイ・アルパの名曲集もすばらしいが、ここにはあえてアルゼンチン・タンゴ集をあげたい。これまでにも同種の企画はあったが、この人の演奏は群を抜いている。おなじみの「ラ・クンパルシータ」もいいが、「パリのカナロ」のバンドネオン変奏をアルパで弾きまくる彼の超絶技巧にはたまげた。それでいて音楽性の高さにもすごいものがある。 |
 ドリーム21/ビクター (PRCD-1671) |
「ベサメ・ムーチョ/キエレメ・ム−チョ」魅惑のラテン〜クレバノフ/ストリングス ぼくはいわゆるオ−ディオ・ファンではないが、この録音で聴いた「ベサメ・ムーチョ」の音の素晴らしさにはぶっ飛んだ。それもそのはずで、LPが全盛だった当時にはオ−ディオ・チェックのための定盤となっていた1枚である。それがいまK2 24ビットのニュー・マスタリングCDとして復刻されたのだが、あのふくよかだったサウンドはさらなる艶をともなって鮮やかに甦っており、聴いていてなんともゴージャスな気分に浸れる。 1917 年シカゴに生まれたロシア系アメリカ人で、バイオリン奏者としてシカゴやイリノイ、さらにNBCなどの交響楽団を経て自分の楽団を結成して活躍したハ−マン・クレバノフは、レコーディング用のオーケストラとしてクレバノフ・ストリングスを率いてイージー・リスニングに新風を吹き込んだが、本作はその彼を代表するラテン・アルバムとして持っていたい1枚。 |
| ホーム | インフォメーション | 注目のアーティスト | ミュージック・プラザ | ラテン音楽ベスト100 |竹村淳の言いたい放題 |