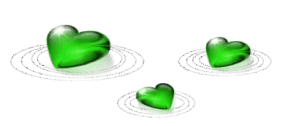
嫉妬③
翌日は誰も特に予定を入れていなかったので――最初からショッピングの日に充てられていたので――各々自由に過ごすことになった。
他の003たちがどこに行って何を買うなど楽しく話しているなか、超銀フランソワーズはそうっと部屋を抜け出した。
何しろ、考えなければならないことが多すぎる。
自分たちのこの旅行を楽しむことはもちろんだけど、それ以外のことが気になって仕方がないのだ。
それを解決しない限り、自分は今日このとき以降の旅行を楽しむことなどきっとできやしない。
だからこれからそれを解決しに行くつもりであった。
「それ」とはつまり――ジョーのことである。
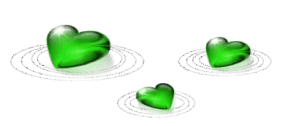
――まったく、もう。
どうしてこう見張りみたいなことをするのかしら、あのひとって。
思えば、遠く離れた地にいるにも拘らず彼は常にそうだった。
気付けばそこにいて。
気付かなくても、そこにいる。
……筋金入りのストーカーだわ。
そのストーカーっぷりに一度は疑ったこともある。ギルモア博士に言って、内緒で自分に発信機か何かつけたのではないか、と。
まさかそこまではしないだろうという結論に達してはいるのだけれど、こんなことが続くと本当はついているのではないかと思う事もしばしばだった。
しかも、彼の気配の消し方はそれは見事なもので、それこそフランソワーズが「気付いたら」そこに居るのである。
それまでどこからどう接近してきたのかさっぱりわからない。
そのあたり、彼が優れたサイボーグである以上にストーカーたる素質があるのではないかと疑うところであった。
そして。
――いない。
ホテルの窓から見た時は、確かにこのあたりに居たはずである。それは間違いない。が、なぜか近くに来ると――ジョーがどこに潜んでいるのかさっぱりわからなくなってしまうのだった。
――んもう。いったいどこに隠れているの?
ホテルを出てからずっと彼をサーチしているわけにもいかず、特に「目」を使ってはいなかった。
それがいけなかった。
きっと、ここで見つかったら説教されさっさと日本へ帰されると思ったのだろう。それで姿を見せない。が、ということは、彼はこれから先も003一行について回る気まんまんということになる。
それは困る。
何をしても見張られていると思うと落ち着かない。そんなのは、二人で旅行するときだけでたくさんである。
フランソワーズは四方を探るようにざっと見回し、諦めて歩き出した。
姿を見せないなら仕方がない。自分は普通に買い物を楽しもう。そのうちきっとどこかで姿を見せるだろうから。
そう思い、並んでいる店のウインドウを見ながら歩いた。
数分後。
アクセサリーショップの前でふと足を止めた時だった。
「――気に入ったのがあったらプレゼントしようか?」
耳元で声がした。
「別に。ただ見ていただけですからお構いなく」
「ふぅん。きみに似合いそうだけどなぁ」
「あら、どれが?」
「そこの手前の」
「…趣味悪い」
「そうかなぁ。きみ、似たのを持ってるだろう」
「誰かさんのプレゼントで仕方なく」
「気に入ったって言ってたじゃないか」
「そう言わないと拗ねるから」
「…酷いなぁ」
「酷いのはあなたでしょう」
そう言うとフランソワーズはウインドウから目を離して横に立っている男性を見た。
「そのひと、痛がっているじゃない」
「ん?」
フランソワーズの横に立っている男性は、なぜか傍らの男の腕を捻り挙げていたのだった。
「肩の関節が外れそうよ」
「そんなに力入れてないよ」
「そうかしら」
「ああ」
「…そのひと、何をしたの」
「きみのバッグをひったくろうとした。そんなことより、本当に似合うと思うけどな、それ」
「そうかしら」
「うん。目の色と合ってる」
「…ブレスレットを買うためにここに来たんじゃないでしょう」
「さあ。どうかな」
涼しい顔で言う男はジョーであった。
片手でひったくり未遂犯を捕まえたまま平然と会話を続けている。その未遂犯はいよいよ辛そうで真っ青だった。
「…離してあげたら?未遂なんだし」
「でもきみを狙ったのは許せないな」
「いいじゃない、未遂だったんだし」
「よくないさ。これから警察に行って」
「…未遂よ?」
「でもきっと常習犯だ」
「どうしても警察に行くの?」
「ああ。許せないね」
「せっかくふたりっきりなのに?」
「ああ。きみを狙った男なぞ――………えっ?」
蒼い瞳と茶色い瞳が見つめ合った。
「…ええと」
「せっかくこれからデートできるのにジョーは警察に行くのね」
「え、いや」
「ざーんねん」
「いや、行かないよ警察なんか。ほら、いく用事なんて何も無い」
ジョーは両手を広げてみせた。未遂犯はいつの間にか消えている。
「ね?」
にこにこしているその顔を見つめ、フランソワーズは心中息をついた。
――まったくもう。
「それよりどうしてここにいるの、ジョー。あなたイタリアに来るなんて言ってなかったし、ひとの旅行についてくるなんて」
「デートの手始めにまずこれを買おう、行こうフランソワーズ」
「え?ちょっと話を聞いて――」
有無を言わさず腕を捉まれ、フランソワーズは店内に連行されていた。ジョーを見つけたら言おうと思っていたことを半分も言わないうちに。
――でも…まぁ、いいわ。
今日いちにちデートしていれば訊く機会もあるだろう。
それに何より。
SPがついていると思えば贅沢な旅行だわ。それも――私専属のSPだし。
そう思った。
だから。
――会いたかったっていうのは内緒。