
「日本に来る理由」

久しぶりにフランソワーズに会った。彼女が日本に来たのだ。
何故来たのかその理由は知らない。
きっと何か僕には予想もできない理由があってやってきたのだろう。
彼女は僕と違って、会いたいから来たなどということは無いのだ。
なにしろ彼女は常に理性的であり、僕のようなばかみたいな衝動に突き動かされた行動などしないからだ。
ともかく、彼女はやって来た。
そして当然のように僕の部屋に泊まった。
「――フランソワーズ。今日の予定は?」
最近までまだまだ残暑といっていいくらい暑かったのに、彼岸を過ぎた途端に秋になった。
この日本の天候は住んでいる者でも対応が難しい。予定があるだろうフランソワーズは大丈夫だろうか。
じっと窓の方を見ていたフランソワーズがこちらを向いた。
「……ええ。そうね……」
そのまま小さくあくびをすると僕の腕にもぐりこんだ。
「え、と。出かけるんじゃないのかな」
「ええ、そうよ」
そうだよな。
繰り返して言うが、フランソワーズが何の理由もなく日本に来るはずがない。
だから初日からあれこれ予定が山盛りのはずなのだ。
「その予定を訊いたんだけど」
訊いたらダメだったのか?
「――ん……予定、ね」
けれどもフランソワーズはむにゃむにゃ言うばかりでいっこうに要領を得ない。
これは――僕には言えない予定、ってことか。
そう思うのが妥当だろう。だとすれば、これ以上追求するのは不粋というものだ。
――別にいいさ。そんなに予定を知りたかったわけでもないし。単に、――そう、目覚めたあとの朝の会話ってやつだ。
しかし、フランソワーズは目覚める気はないようで、そのまま僕の胸のなかですうすう眠り始めた。
おいおい、予定はどうした。いったい何時からどこで何をする。
こうして寝ていて大丈夫なのか?
「……ふ」
名前を呼びかけて思いとどまった。
大体、どうして僕がやきもきしなければならないんだ。
彼女の予定におそらく僕は組み込まれていないだろう(組み込まれているなら予定を知っている)。
だったら、彼女がいつのどのような約束に遅れようが忘れようがそれは僕には関係ないということだ。全て彼女の自己責任だ。
知るもんか。
僕も目を閉じた。
眠ってしまおう。大体、こんなに朝早く目が覚めること自体おかしい。今は朝の六時だ。
僕のほうこそ、今日の予定なんかないのだし。
固い決意とともにフランソワーズを抱き締め、眠りについた。
ふん、知るもんか。僕は寝る。
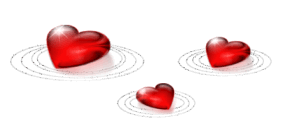
「……ううん」
なんだ。
――なんだ?
な、なんなんだっ?
僕は異常事態に気がついて目が覚めた。
がしかし、声が出ない。
「――むぅ」
――口を塞がれていた。
「……あら、起きちゃった」
のほほんとした声とともに声が出せるようになった。
「ふ、フランソワーズ、いったいっ……」
至近距離にフランソワーズの顔がある。もっと言うと、唇が。
僕はフランソワーズに唇を塞がれていたのだ。彼女の唇によって。
端的に言うとキスされていた。
「なっ……」
フランソワーズは僕の胸の上に上半身をあずけ、楽しそうに見下ろしている。
「ジョーったら、ずうっと寝てるんだもの」
「……二度寝したのはきみのほうが先だろ」
「寝てないわよ?目を閉じていただけ」
嘘をつけ。
「いいじゃない。別に予定があるわけでもないし」
「えっ?」
「あ、でも予定があるといえばあるかしら」
楽しそうなフランソワーズの表情。でもどこか――何か企んでいるように見えるのは何故だろう。
「……だからその予定を訊いてたのに」
教えてくれなかっただろうと言うと、フランソワーズはちょっと目をみはってそして、あろうことか答える代わりに僕の唇を塞いだのだ。
いったいどうしたんだフランソワーズ。
「いいじゃない。減るもんじゃないでしょう」
「そうだが、しかし」
「そんなに私の予定が気になるの?」
「……まあな」
「じゃあ教えてあげる。どうして私が日本に来たのか」
そう言うとフランソワーズは再び僕にキスをした。
こういうのはもちろん嫌いではないが、あまりにもいつもの彼女とは――違うような気がして落ち着かない。
いや、そうでもないだろうか?
僕は彼女にキスされている間、記憶を手繰っていた。
過去にこういう彼女はいただろうか。――いない。――いや待て。
いた。
「……あのね。ジョーに」
ストップ。
「うん。わかった」
そう言うと、僕はフランソワーズを抱き締めた。
フランソワーズは微笑むと再び僕にキスを始めた。
フランソワーズは僕に甘えるために日本に来たのだ。
いったい何があったのかは知らない。たぶんフランソワーズも教えてはくれないだろう。
でもそれでいい。
何かあったのだとしても、その結果、落ち着くために僕を思いだして僕の元へ来るのなら。
それでじゅうぶんだった。

でも。
僕はフランソワーズから何度目かのキスを受けてそれを返しながら考えていた。
そろそろ、一緒に暮らすことを考えたほうがいいかな――と。