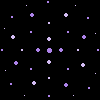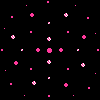
『たぶん恋人同士』
「フランソワーズ、大丈夫?」
手を引いているにも拘らず、振り返った先の人物は人混みに埋もれていた。
今一度手を引き寄せて、やっと――その手の主が現れた。
「大丈夫・・・じゃないわ!」
んもう!と悔しそうに唇を噛む。が、立ち止まったためにその後ろから押されよろける。
ジョーはその身体を庇うように背中に手を回し自分の体の影に入れた。
そうして少しずつ歩を進め、比較的人の少なそうな一角に向かいやっと一息ついた。
「フランソワーズ」
「もうっ・・・足も痛いし、髪もぐちゃぐちゃだし、浴衣だってっ・・・」
確かに酷い有様だった。
履き慣れない草履は鼻緒の部分がこすれて指が赤く擦りむけているし、綺麗にアップにした髪はところどころほつれてしまっている。
挿したかんざしは既にもう無い。浴衣は着崩れはしていないものの、全体的によれよれだった。
「せっかく頑張ったのに・・・」
うつむいたその瞳に涙の粒が盛り上がった。
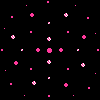
今日は花火大会。
それこそ指折り数えて楽しみにしていたのだ。
しかもフランソワーズは今日のために浴衣の準備もして。
なのに、予想外の混み具合で、花火だってやっと――歩きながら見れたのだ。
落ち着かないこと甚だしい。
「ごめん。僕がもうちょっと調べて、ちゃんと場所も取っておけばよかったね」
ジョーもしょんぼりとうなだれた。
フランソワーズがせっかく綺麗にしてきたのに台無しにしてしまった。
それが悔しかった。
「・・・足、痛いよね」
かがんで擦りむけているところを調べる。
気丈な顔をしているが、かなり痛いのは間違いないだろう。
「いま、何か履くものを買ってくるから」
「待って。買うっていっても一体どこで?」
「どこ――って・・・」
店など開いてないし、コンビニなんてものはこの辺にはないのだった。
「・・・大丈夫よ。このくらい」
「でも」
「平気。知ってる?おしゃれの基本は我慢なのよ」
けなげにも笑ってみせるフランソワーズに、ジョーは口元を引き締めた。
せっかく綺麗に整えてきたのにと悔し泣きしそうだったフランソワーズ。だけど今は笑っている。
それは、ジョーが落ち込んだからに他ならない。
自分だって悔しくて悲しいくせに、ジョーが落ち込むと自分のことは後回しにして全部我慢してしまう。
それがフランソワーズだった。
「そういうの、やせ我慢って言うんだよ。僕は嫌いだな。そういうの」
そう言うとフランソワーズの背と膝の裏に手をかけて、あっという間に抱き上げてしまった。
「ちょっ・・・ジョー!?」
「しっ。黙って」
「だって」
恥ずかしいわと周囲を気にするフランソワーズ。
しかし、流れてゆく人混みはお互いを見失わないようにするだけで精一杯なようで、誰も彼らに注意を払わなかった。
それに、実は花火大会はまだ終わっていないのだ。
だからみんな空を見ている。誰もこちらを見てなどいない。
「平気だよ。僕がこのまま行くから、フランソワーズは花火を見てて」
「でも」
「誰も僕たちなんて見てないし、見たって――ああ、仲のいい、・・・・って思うだけだよ」
「仲のいい――何?」
「えっ」
「よく聞こえなかったわ」
「・・・それは」
ジョーは顎を引くと、前髪の奥に隠れてしまった。
「・・・なんでもないよ。さ、行くよ」
フランソワーズはジョーの首筋に手をかけて、一瞬彼の耳元で呟いた。
そうしてから上半身を捻って正面を向いて、頭上の花火を楽しんだ。
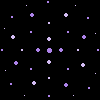
「・・・ずるいのはどっちだよ」
ジョーの声は喧騒に紛れて聞こえない。
――ずるいわ。私たちは仲のいい「仲間」なの?それとも・・・?
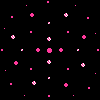
「――恋人同士に決まってるじゃないか。・・・たぶん」
そう小さく口の中で呟いたら、ジョーの首筋に置かれたフランソワーズの手がぴくりと動いた。
――聞こえたのだろうか。
それとも無関係だろうか。
フランソワーズの力なら、喧騒の中でもジョーの声を捉えることは簡単で――
すると、まるで心を読んだように蒼い瞳がくるりとこちらを向いた。
「たぶんなの?ジョー」
「え・・・と」
聞こえてたのか・・・と頬を赤らめる。
「ジョー?」
「・・・たぶんじゃなくて、その」
「その?」
「ちゃんと・・・恋人同士。です」