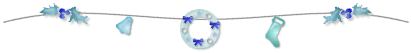|
頭上できらきら輝いているイルミネーション。
私はその美しさに目を奪われ、足を止めた。
と、その途端。
乱暴に腕を引かれ、思わずつんのめりそうになった――ううん、思い切りつんのめってしまった。
そして腕を引いた相手の肩におでこをぶつけた。
「ほら。フランソワーズ。こんな人混みで立ち止まっちゃ駄目だ」
「ごめんなさい。でも」
「でもはナシだ」
ナインが怒ったように乱暴に手を引いて、すたすた歩き出す。
私は小走りになってついていくのが精一杯。
なんだか、全然ロマンチックじゃない。
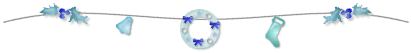
今日は、以前から行きたいなと思っていた表参道にやってきていた。
クリスマスシーズン真っ只中ということで、物凄い人混みだった。
みんなイルミネーションが目あてだから、時々立ち止まったり、ゆっくり歩いたり、緩急さまざま。
しかも前を向いてなんかいないから、気をつけないと常に誰かにぶつかってしまいそう。
でも、怒るひとなんていない。みんな一様に笑顔で楽しそう。
だから私も楽しくて嬉しくてわくわくしていたのだけど――。
着いてから、ナインはずっと不機嫌そうだった。
実際に不機嫌なのかどうか確かめたわけじゃないけれど、にこりともしないしお喋りもしない。
その横顔は強張っていて、不機嫌なのは確認するまでもなさそうだった。
ナインが人混みが嫌いなの、知ってるけれど。でも…せっかく一緒に来たのにと少し寂しくなった。
イルミネーションを見てはしゃいでいるのは私だけで、ナインは渋々来てくれただけで……。
私はナインと一緒にいるだけで――ううん。ナインが一緒にいるから、それだけで自然に嬉しくなってしまうのだけど、でもそんなはしゃぎようは彼からみれば子供っぽくてつきあいきれないのだろう。
だから、それが寂しいなんて思うこと自体子供である証明。ナインはもっと大人の女性が好きなんだから。
でも、大人の女性ってこういう時どう楽しむんだろう…?
私はもっとゆっくりイルミネーションを見たかったけれど、ナインは歩く速度を緩めてくれない。
どうあってもさっさと人ごみから抜け出したいみたいでどんどん歩いてゆく。
私の目にはイルミネーションが流れるように映るだけ。どんな装飾をされているのか、何色なのか――なんて全然わからない。
これって来た意味があるのかしら。
「ねぇ、ジョー」
思い切って話しかけてみた。
「何」
もちろんナインは無視なんてしない。でも、かといってにっこり笑って振り返ることもしなかった。
歩く速度はそのままで前を向いたまま答えただけ。
「…私、もっとゆっくり見たいんだけど」
「…」
「ジョーがこういう場所、好きじゃないの知ってるけど、でも…」
「…」
ナインは無言で歩き続ける。
こんな速度で歩いていたら、イルミネーションなんてあっという間に終わってしまう。
実際、イルミネーションの終点はもうすぐだった。
「ねえ、ジョー」
けれどもナインは私の声が聞こえていないみたいに何も言わない。
聞こえていないわけではないだろうと思う。だってさっきはちゃんと返事をしてくれたし。
「ジョーったら」
手はしっかり繋がっているのに、心はどこか遠くにあるみたいな感じだった。
そう――ナインは何か他のことを考えているみたいで。
心ここにあらず。
まさにそんな様子だった。
一緒にいるのに。
こうして繋いだ手は温かいのに。
なのに。
ナインの心はいま、ここにいない。

そしてとうとう終点に来てしまった。
全然楽しくないデート。これもデートと言えるのなら、間違いなく私の人生最悪のデートだろう。
手を繋いでいるという物理的な結びつきはあるものの、ナインの声も聞いてないし目をみることもなかった。
それでも「一緒に歩いた」という客観的事実は残る。傍から見れば立派にデート。
でも。
こんなのデートじゃない。ただ連行されただけだもの。
私はもっと、ナインと他愛もない話をしながら、彼の顔を見て彼の目をみて彼の声を聞きたかった。
それがなかったら、イルミネーションなんて楽しくもなんとも――
――情けなくて、涙が出てきた。
こんなのってない。
一緒にいるのに。
なのに。
どうして私はいま、ひとりぼっちなの?
イルミネーションの終点でナインは足を止めていた。
そして、よし。とひとつ頷いた。
なにが「よし」なのか、全然わからない。
もうナインなんか知らない。
「フランソワーズ」
初めてナインがこちらを向いた。
私はとっさに眼を伏せて泣いているのを誤魔化した。
「――フランソワーズ、どうかした?」
「なんでもないわ」
「でも」
「なんでもないの。ちょっと目にゴミが入っただけで」
「ゴミ?ちょっと見せてみろ」
「いいの、大丈夫」
「でも」
「大丈夫だったら!」
強引にナインの手を振り払った。驚いた顔のナイン。
「ええと…フランソワーズ?」
謝らない。だって、私は悪くないもの。
「目が痛い?」
でもナインは怒ったりせず、優しく言うのだ。目にゴミが入って痛いから、私が不機嫌になっていると心配して。
だから私は黙って首を横に振った。それしかできない。
どうあっても私の今の気持ちなんて、ナインにはわからないのだから。
「だったらいいけど。…見える?これからが本番なんだから」
「本番?」
って、何?
「ふふん。この僕を誰だと思ってるんだい?」
「誰って…」
「いま、ざっと歩いて大体の様子は掴めた。一番いい場所もわかったし混んでいる所や危険な場所も把握した。あとは僕に任せてくれれば大丈夫だ。さ、行くよ?」
「行くって…どこ、へ?」
「ええっ?何言ってるんだいフランソワーズ。イルミネーションを見に来たんだろ?」
「…そうだけど」
「だったらそれを見なくてどうする」
だって。
「それに、ほら。見てごらん。みんな駅が向こうにあるから向こうからこっちに向かって歩いてくるだろう?実際、僕たちもそうしてここまで来た」
「ええ」
「でも、僕たちはここから逆に向こうにむかって見るんだ。少しこちらのほうが高いからよく見えるし、それに」
そこでナインはちょっと口をつぐんだ。
不思議に思って彼を見ると、なんだか少し顔が赤くなっていた。
「――それに」
私の視線に気付いて、ふいっと顔を逸らしてしまう。
「こっちから見たほうが似てるんだ。その、――パリと」
後半は早口になって、私がその意味を考える前にさっさと手をとって歩きだしてしまった。
でも今度はずいぶんゆっくりで。だから私はナインの言葉をゆっくり考えることができた。
――パリを思い出すわ。
テレビでこのイルミネーションを観てそう言ったのは私。
ずいぶん前だったのに、ナインはそれを覚えていてくれて、それで――

せっかくのイルミネーションなのに、パリに似ているのに、私の目にはどれもこれもぼやけて滲んで見えた。
|