「チョコレート」
バレンタインデーとその後のお話
弁当の蓋を開けたらピンクと茶色が見えたので、ジョーは慌てて蓋を閉じた。 事の発端は2月17日のお弁当だった。 いつものようにフランソワーズから受取り、昼に包みを開いた。いつもの弁当箱である。 「あれ?」 ごはんの中央にハートの何か。 「なんで」 もちろん、別添の容器におかずは入っている。 帰宅して彼女にそう告げたジョーだったが、返ってきた答えは笑えるものではなかった。 「あら、冗談じゃないわよ?もちろん」 笑顔のフランソワーズだが目は笑っていない。 「ジョーは好きでしょう。チョコレート」 お弁当に入っているのは好きじゃない。更に言うと、ごはんとチョコレートは合わないと思う。ごはんチョコレート推進事業には申し訳ないが(そんな事業があればの話)。 「毎日食べてもいいんでしょう?」 フランソワーズの視線の先には山積みされたチョコレートがあった。 「なくなるまで食べるのよね」 バレンタインデーの夜からフランソワーズはご機嫌斜めなのだった。
―1―
知らず溜め息が出る。
……今日で7日目かぁ…
ごはんにチョコレートなんて冗談じゃない。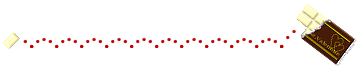
今日はなにかなと頬を緩めつつ蓋を開けた。いつものように。
なんだろうとよくよく見ると、それはチョコレートだった。チョコレートがごはんの真ん中に埋め込んである。
が、しかし。
なぜ白いごはんの上に特大チョコレートが載っているのか。ジョーには理解できなかった。
できなかったので、これはフランソワーズの可愛い冗談なのだろうと決めつけた。
バレンタインデーの後だし、残ったチョコレートをどうするか悩んで驚かそうと思ったのかもしれない。
「えっ」
「え、いや…」
「たくさん貰ってきたもんね?チョコレート」
狭い部屋にその存在感はかなりのものだ。
「……」
バレンタインデーの夜。 そんな日常なのに。 ジョーの紙袋の中には、バレンタインデーのチョコレートが詰まっていたのだった。 「…これ、なあに?」 既に透視してわかってはいたものの、フランソワーズは好奇心旺盛なふりで可愛く訊いて見た。 「え。チョコレート。貰ったんだ」 ジョーの勤務先の社長の娘で既婚者である。 「それから?」 そんなわけはないだろう。 「で?」 フランソワーズの眉がぴくりと動く。 「あれ?中学生かな?」 ジョーは悪びれず首を捻ってどうでもいいことを考えている。フランソワーズにとって、女子高生であろうが女子中学生であろうが、女子大学生であろうがOLさんであろうがどうでもいい。 「なんか、余ったからって」 ばかじゃない。 フランソワーズは、興味なさそうに紙袋を渡すジョーを唖然と見つめた。 否。 ここにいる。 「…見てもいい?」 フランソワーズが袋を開けてひとつずつ取り出すと、それらはどう見ても本命チョコに他ならなかった。 「どうするの、これ」 きょとんと答えるジョーに、でしょうねと小さく呟きフランソワーズは夕食の支度に戻った。本命チョコを唯々諾々と貰ってくるジョーに呆れながら。そして、その本命チョコにいったいどんな返事をするのだろうかと思いながら。
―2―
帰宅したジョーが紙袋を提げていたのを見てフランソワーズは唖然とした。
レーサー時代ならともかく、今は目立たず普通の生活をしているのだ。
しかもこの町に越してきてまだ一年経っていない。
既にこの町でこの生活に馴染んできているとはいえ、知り合いは多くは無い。せいぜい、お互いの勤め先のひととこのアパートの住人くらいのものだ。あとは、買い物に行く商店街のひとが顔見知り程度であって、いうなれば殆どが他人だ。
こころもち首を右に傾げ、女子力アップである。
「ふうん…誰に?」
「え、と…勤務先のお嬢さん」
「それから…お客さん。たまたまチョコレートがあるから、あげるわって」
「……ふうん」
バレンタインデーに「たまたま」チョコレートを持っているはずがない。
最初からジョーに渡すのが目的に決まっている。
「え?」
「それから?」
「それから…帰る途中で女子高生から」
要は彼女たちがわざわざバレンタインデーにジョーにチョコレートを渡したという事実が問題なのだ。
帰り道に貰ったということは、以前からジョーの行動がリサーチされていて待ち伏せされたことに他ならない。
余ったからあげるなんて言われて信じるばかがどこにいるというのだろう。
「ウン」
贔屓目に見て義理チョコがふたつくらいか。あとの10個は本命チョコに間違いない。リボンやら花やらがあしらってあって、カードまでついているのだ。
「え。食べるよ」
チョコレートを噛み締めつつ、ジョーはバレンタインデーの夜のそんな遣り取りをぼんやり思い返していた。 いったいなぜフランソワーズはお弁当にチョコレートを入れようなんて思いついたのだろうか。 もちろん、ジョーの返事が発端である。 ふつうに考えて、チョコレートは食べ物なのだから食べると答えるのが正解である。 が、しかし。 あの時、ジョーが食べるよと答えた後からなのだ。フランソワーズの機嫌が悪くなったのは。 まさか、チョコレートのせいじゃないよな。 そう、だって、たかがチョコレートなのだ。余ったからあげるとかたまたま持っていたからあげると言われて、残り物処理のように渡されたチョコレート。ジョーにとっても思いいれなどない。むしろ、フランソワーズからチョコレートを貰えずにいることのほうが落ち着かない。 ……バレンタインデーだったのになあ。 もしかしたら、日本のバレンタインデーを知らないのかもしれない。 ジョーは7日目の「ごはんチョコレート弁当」を食べ終えると立ち上がった。
―3―
頭の片隅では、やっぱりごはんとチョコレートは合わないなあと再確認しつつ。
あの夜、このチョコレートどうするのと訊かれ、食べるよと答えた。
が、しかし。
ただそれだけのことだった。
ジョーは間違ったことは言っていない。
それは今、チョコレートの名残を伴ったごはんを口に入れても揺るぎはしない。
もちろん、彼女は何も言いはしない。意地悪なことも言わないし、嫌な顔をしたりもしない。いつも笑顔である。
が――その笑顔が、こわい。
しかも。
あの夜から、ジョーはフランソワーズに振られ続けているのだ。体調が悪いとかそんな気分じゃないのとか今日は物凄く眠いのとか色々な理由で。
そう思ったから、フランソワーズからチョコを貰ってないことに気付かないふりをしているけれど。
なんだか胸の奥がもやもやするのだ。
否、それはチョコレート風味のごはんが胸につかえているせいかもしれない。やはり、ごはんにチョコレートは合わない。断じて、合いはしない(ごはんチョコレート委員会には申し訳ないが)。
ちょうど昼休みも終わりであった。
今日もお弁当は完食だった。 ジョーはいつもと変わりがない。 「……」 なんだか頭痛がしてきてフランソワーズは手を止めた。 そんなできた彼女は漫画やドラマの中にしかいない。 ジョーがどう思っているのか知らないが、フランソワーズは断じて物分かりの良い彼女などではないのである。 「もうっ…ジョーのばか」
―4―
空の弁当箱を洗いながら、フランソワーズはさてどうしたものかと内心あれこれ悩んでいた。
嫌がらせのように(実際は嫌がらせなのだが)弁当のごはんにバレンタインチョコを埋め込んで約二週間。
最初の頃は、さすがに疑問だったらしく遠回しに探りをいれてきたジョーだったが、途中からは何も言わなくなった。きっと何かを察したのだろう。
が。
リアクションは何も無かった。
そして、何も無いままバレンタインチョコは終了したのだ。
これでは、せっかく嫌がらせのようなものをしたのに意味が無い。
フランソワーズとしては、いよいよジョーがあの弁当は何なんだと詰め寄ってくれたら、本命チョコをさらりと貰ってくる彼氏なんて普通じゃない私を何だと思っているのと本音をぶつけることができた。
が、それは儚い願いだった。
きっと、ごはんにチョコというのも変わったデコレーションだなあとしか思ってないのだろう。自分がチョコを食べると言ったからフランソワーズがそうしたんだろうな斬新だなあと。
まったく、なんなのだ。
このままでは自分は「彼氏が本命チョコを貰ってきてもヤキモチやかないできた彼女」になってしまう。
今だって、物凄く妬いている。

その日、帰宅すると部屋中甘い香りに満たされていた。 「ただいま。…何してるの」 遠足か何かあっただろうか。 「…クッキーの即売会?」 しかし、ジョーのそんな的外れの問いに答える気はさらさらないようでフランソワーズは曖昧に笑っただけだった。 「これ、フランソワーズが作ったの」 なぜ彼女が突然クッキーを作る熱にうかされたのか知らないが、彼女が楽しいなら理由など要らないジョーであった。 「一枚貰っていい?」 当然貰えるものと思って手を伸ばした。 が、 「だめよ!」 その手を叩かれ、ジョーはびっくりしたようにフランソワーズを見た。 「えっ」 やはり即売会か? 「明日、ジョーが持って行くのよ」 即売会があるなんて知らないし、場所もわからない。 するとフランソワーズは艶やかに微笑んだ。 「先日、チョコレートをくれたみなさんに渡すのよもちろん」
―5―
なんだろうと思っていたら、山盛りのクッキーを発見した。そして、そのクッキーを小さな透明な袋に個分けしてリボンをかけているフランソワーズも。
「おかえりなさい。明日の準備」
「明日?」
いや、遠足にしてはクッキーのラッピングが丁寧だ。売り物みたいに。
「ええ」
「凄いなあ」
「オーブントースターしかないから大変だったけど楽しかったわ」
「ふうん…」
「ジョーの分は無いの」
「え。だって、じゃあこのクッキーは」
「へ?どこに?」
「え?」
「ホワイトデーですもの」
3月14日。 そんなの無理だよなぁ。 クッキーの入った手提げをうらめしそうに見て溜め息をついた。 「あのこれ、もしよかったら」 「あ。もしかしてチョコくれましたよね?」 「この前、チョコくれたよね。これ、お返しなんだけど…」 ジョーの心配は杞憂だった。 ジョーとしては不思議でならなかった。
―6―
わけもわからずフランソワーズ手製のクッキーを持たされ家を出たジョーである。昨夜、チョコをくれたみなさんへ渡すのよと言われたが、それは無理な相談だろうとジョーは思っていた。
誰からもらったのかなんて、そもそも憶えていないのだ。憶えてない相手にどうやって渡せというのだろう。
しかしフランソワーズは全く心配していないようだった。きっとわかるわよと謎めいた微笑みでジョーを送り出した。
3月といってもまだまだ寒い朝であった。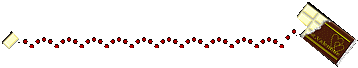
「え!うそ!お返しを頂けるなんてっありがとうございます!……あれ? あの、このクッキーって手作り……」
「うん。フランソワーズが作ったんだ」
「フランソワーズ…さん?」
「うん。昨夜」
「昨夜…?」
「一緒に住んでるんだ」
「あ、……そうなんですか」
「あら、憶えててくれたのね。嬉しいわ」
「これ。僕から」
「ありがとう…ん?手作りクッキー?」
「昨夜フランソワーズが作ったんです」
「フランソワーズ…?あら、やっぱり彼女いたのね」
「うそ!マジ?」
「超嬉しい!」
「ヤバイ、どうしよう!」
「ん?ちょっと待って、これって手作りジャン」
「まさか島村さんが作ったとか?」
「料理男子!萌えるんですけど!」
「僕じゃないよ。作ったのはフランソワーズ」
「誰?」
「まさか彼女?」
「ほらあ、やっぱりいるんじゃん」
「いないわけないって言ったでしょー?」
視界の隅でもじもじとこちらの様子を窺う女子は、もれなくチョコをくれた女子であった。
ジョーが気がつくと彼女たちは小走りに近付いてきたので、ジョーとしてもお返しのクッキーを渡す作業は楽だった。が、全員が最初は喜び、そしてクッキーを見て肩を落とす。その繰り返しである。
今頃、クッキーを渡している頃よね。 パン屋で働きながら、フランソワーズはその光景を頭の片隅で確認していた。もう使わないと決めた力だけれど、今日はちゃんと見届けなくてはならない。 自分がどんなに意地悪な事をしたのか、わかっているから。 本命チョコを渡したら、相手は笑顔で受け取ってくれた。そしてホワイトデーにはお返しをくれた…けれど。 フランソワーズは溜め息をついた。 こんなの、考えられるシチュエーションの中でも最悪のものではなかろうか。 でも いま、それをしているのは自分なのだ…… 自分は悪くない。 だから。 ごめんね、彼女がいるんだ なんて、きっと言わない(言えない)彼氏に、受け取った相手が「あぁ彼女がいるんだ」と察してくれるように誘導するのは、これしか方法が無かったのだ。 だから、私は悪くない。 そう何度も自分にいい聞かせた。 フランソワーズは帰る足取りも重く、とぼとぼ歩いていた。 本当なら、この役をやるのはジョーのはずなのに。なのに彼は、なんにもわかっていないのだ。 本命チョコをさらりと受取り持ち帰った日の自分の気持ち。 ジョーはなんにもわかっていない。
―7―![]()
その「お返しのクッキー」は、彼の恋人の手作りだった。
何も知らずにクッキーを受けとる側のダメージは大きい。きっと自分だったら泣いてしまうだろう。
フランソワーズの胸は痛んだ。
悪いのは、本命チョコを悪びれもせず受け取ってしまったジョーのはずだ。
更に言えば、本命チョコなのにそうと伝えず「余ったから」「ちょうど持っていたから」などと偽って渡した彼女たちである。
が、しかし。
彼女たちにしてみれば「バレンタインデー」に「たまたま」チョコを持っていたからあげる、なんてことがあるわけないとわかるでしょう普通。
というわけだ。
バレンタインデーに本命チョコを渡すという照れもあって、わざとそう言う場合もあるだろう。そしてそれらは全て暗黙の了解なのである。まさか、意味のわからない男子などいるわけない。
そう思っている。
だから、はっきり本命チョコだと言わなかったとしても責められるべきではない。
となると、やはり責められるべきはジョーなのだ。日本男子でありながら、そういう機微を理解しない鈍さはいかがなものだろう。
が、しかし。
そこもまたジョーのジョーたる所以なのだ。
そういう鈍いところも含めてジョーなのである。
でも。
もしも自分がチョコを渡した側だったらと想像してみると、やはりこんな風に彼女の存在を知らされるのは辛かった。恥ずかしいやら情けないやら。だったらどうして最初からそう言ってくれなかったのだろう。知らされていたら、いまこんないたたまれない気持ちにはならなかったのに。
きっとそう思うだろう。
そして、今日、複数の女の子にそんな思いをさせたのは誰でもない、自分なのだ。
最悪のホワイトデーだった。
それらのチョコを連日弁当に入れたその意味。
昨夜、お返しクッキーを焼いていた時の気持ち。
そして今朝、それをジョーに渡した時に予想した今の気持ちの自分。
フランソワーズが帰宅するとジョーは既に帰っていた。 そうではない。なんだかジョーの顔を見るのが辛くて、わざとゆっくり帰ってきたのだ。 「――お腹空いたでしょ?すぐごはんにするわね」 そう言ってジョーが指差したのは。 「えっ……」 それは、フランソワーズの手製クッキーだった。 「え、どうして」 昨夜、ラッピングして別にしまっておいたはずなのに。 「腹減ったなあってあちこち見てたらみつけた。何?食べたらまずかった?」 今日一日、辛かった。 なのに、どうして勝手に食べちゃうの。 「え。だってフランソワーズのクッキーだし」 ジョーはなんにもわかってない。どんな気持ちでこのクッキーを作ったのか、なんにもなんにもわかってない。 「……フランソワーズ。もしかして、誰かにあげるつもりだった?」 少し沈んだジョーの声。 「……そうよ」 それっきり、ジョーは黙った。 気まずい沈黙が降りる。 クッキーは五個入りで、残ったのはひとつだった。 やはり、ジョーは何もわかっていない。 誰から貰ってなくても、覚えていない。 残りの一枚は自分で食べてしまおうとフランソワーズがクッキーを口に運んだ時。 「……そのクッキー。チョコが入ってるだろ」 ジョーが背を向けたままポツリと言った。 「今日、みんなに渡したのには入ってなかった。だから、」 フランソワーズの手が止まる。 「このクッキーは僕用じゃないかなって思ったんだ」 僕はフランソワーズからチョコを貰ってないし、とぼそぼそ続いた。 「だけど、間違えたみたいだから悪かっ……わっ」 背中にフランソワーズから体当たりされ、ジョーの声が詰まった。 「なっ、なに?どうした?」 泣いてるじゃないか。 「なんでもないわよ、もう…ジョーのばか」
―8―
「おかえり。遅かったね」
「そうかしら。いつもと同じよ?」
「そうかなあ」
「ああ、大丈夫。これ食べてたから」
「……」
「これ、昨夜作っていたやつだよね?」
「……」
「ほら、食べちゃだめって言われたけどさ。僕だってフランソワーズのクッキーは食べたいよ」
「……」
「今日はひとにあげるばかりだったし」
「……どうして」
「うん?」
「どうして勝手に食べちゃうのよっ」
他人を故意に傷付けて悩んで、それはジョーのせいなのにと思いつつ、でもジョーには悪気はないのだから仕方がない。そう折り合いをつけてきたのに。
どうして勝手にみつけるの。
わかってないくせに、あっさり食べるなんてひどい。だってこれは、
先刻までの、どこかのんびりしたのとはまるで違う。
「そっか。……ごめん」
フランソワーズはそれを手にとりしみじみと眺めた。
気付いてもいないのだ。
彼にとってバレンタインデーなんて、ただの「なんだかわからないけれど女の子がチョコをくれる日」なのだろう。
誰から貰っても覚えていない。
「いいの」
「えっ、でも」
「なんでもないから」
「なんでもないって、だって」
バレンタインデーの夜。
たくさんの本命チョコを貰って帰ってきたのを見て渡しそびれたチョコレート。
昨夜、それを砕いて焼いたチョコチップクッキー。
なんにもわかってないジョーに何を言って食べさせようか迷いながら帰ってきた。
「でもジョー。来年からは気を付けてね」 フランソワーズを抱き締め、その柔らかさと温かさを堪能しながらジョーが訊く。 「なにって、だから。あっさり本命チョコを貰ったりしないでね?」 フランソワーズの首筋から唇を離し、彼女をまっすぐ見つめるジョーの瞳は真剣だ。 「本命チョコって、本命の彼女から貰うチョコのことだろ」 なに言ってるの、このひと。 寂しそうに言うと、ジョーは再びフランソワーズの首筋に噛みついた。 「え。ちょっと待ってジョー。本命チョコってそういう意味じゃ…」 どうなのだろう? 私、間違ってないわよね…? それともジョーの言うほうが正しいのか。 「……わからないわ」 フランソワーズは混乱した。 「私のチョコ、何日目かのお弁当に入ってたわよ?」
―9―
「なにを?」
「本命チョコ?…貰ってないよ」
「嘘よ。たくさん貰ってきたじゃない」
「貰ってないよ」
「はいはい。そうよね、これ本命チョコですーって言われてないんだもんね」
「いや、そうじゃないだろ、本命チョコって」
え。
「だから僕は貰ってない。フランソワーズがくれなかったから」
いや、しかし。
日本のしきたりには随分馴染んだつもりのフランソワーズであったが、なんだか自信がなくなってきた。
バレンタインデーの本命チョコとは、確か女性が意中のひとに渡すものだったはず。一番好きなひとに。
だとすれば、確かに彼は誰からも本命チョコを貰ってはいないことになる。
が、考えがまとまらないのは、久しぶりに肌を合わせたジョーの体が熱いせいかもしれなかった。
「え。うそっ」
「うそです」
「……」
![]()