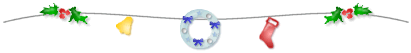
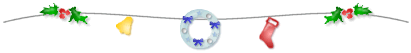
「えっ…出かけるの、お兄ちゃん」
「ったり前だろ。今日はクリスマスイブだぞ」
出かける準備の整った兄を見つめ、フランソワーズはちょっと首を傾げた。
「…教会とか?」
「あのなあ」
そんな妹の頭に手のひらをのせ、
「彼女と過ごすに決まってるだろーが」
「嘘っ、彼女いるの?」
「お前。兄をなんだと思ってる」
――だって。今日は一緒に過ごそうと思ってたから…
「ま、お前も彼氏と過ごすんだろ」
「……」
「いるの、知ってるぞ。今度会わせろ」
――そんなの。
今となってはいるのかいないのか自分でもよくわからない。
そんなフランソワーズを置いて兄はさっさと出かけてしまった。
しんと静まった家。
こんなはずじゃなかったのに。
別にクリスマスだから一緒に過ごさなければいけないというきまりはない。
他の日と何ら変わりはないはずである。だから、いつものように過ごせばいい。本を読んだり音楽を聴いたり。
――でも。
だからこそジョーと一緒にいたかった…と思ってしまうのは、子供っぽい願いだろうか?
それとも、子供のくせに大人のような考え方だろうか?わからない。それに
もう、どうでもいい。
ジョーのばか。
とんでもなく落ち込んでいるのは彼を好きなせいだ。でも――何を落ち込む必要がある?自分は自分の好きなように過ごしていればいいのに。
それもこれも、全部ジョーを好きなせいである。
ならば。
嫌いになろう。そうすれば、彼のことを考えて落ち込んだりあれこれ思い悩むこともなくなる。どうせ彼にとって私の順位は低くて――
自分が思っているくらいの思いを返して欲しいと思ってしまうのは自分勝手だろうか?
「ああもうっ」
そんなことを考えるのが嫌なのにっ。
自室のベッドでじたばたしていたら、携帯電話が着信を知らせた。
「もうっ」
クリスマスイブに何の用よっ
やつあたり気味に放っておく。
が、それはしつこく鳴り響き――留守電に切り替わった。
ほっとしたのも束の間。
再び鳴り始める。留守電に切り替わる。再度鳴る電話。留守電に切り替わる。
というのを数回繰り返したのち、やっと鳴らなくなった。
「……」
そこでやっと手を伸ばし、のろのろと着信を確認した。
ジョーだった。
といって、特に感銘を受けはしない自分がちょっと誇らしかった。ほら、もう嫌いになった。案外簡単だったわね――なんて思って。
でもいちおう伝言は聞いておこうとメッセージを確認した。が、それが再生される前に電話が着信し思わず出てしまった。
『フランソワーズっ』
えっ、ジョー?
『何で電話に出ないんだよ。今日、約束してただろ?』
は?
え?
何言ってんの?
『まあいいや。とにかく出て来いよ。いまちょうど家の前に着いたから』
「えっ?」
![]()
おそるおそる玄関の扉を開けて外の様子を窺うと――確かにそこにジョーはいた。
心なしか怒っているような。否――拗ねてるような顔で。
「フランソワーズ」
「ジョー?えっ、どうしたの」
「どうしたのって何がだよ」
「何がって」
何が?
「約束してただろ。今日は一緒に過ごすって」
「うそ」
そんな覚えはなかった。あれば忘れるはずがない。
「誰かと間違えてるんじゃない」
「は?何言ってんの」
「……女の子と過ごすって言ってたじゃない」
「ああ」
「だったら行けば?」
「だから来たんだろーが」
「ジョーこそ何言ってんの?」
「は?」
「あ。わかった。ふられたんだ。だから二番目か三番目の私でもいいかって思ってそれで」
と言いながら自己嫌悪に陥った。
違う、ジョーはそんなひとじゃない。
「――なんだよそれ」
案の定、低い声が答える。
「二番目とか三番目って何の事だ」
「なんでもない。忘れて」
「――ああそうかよっ」
ふいっと視線を逸らせ、フランソワーズに何かを押し付け踵を返す。
「何よこれ」
「やる。いちおうクリスマスプレゼントってやつ」
「え。要らないわよ、一番好きなひとにあげたらいいじゃない」
「――だから」
怒った声とともに振り返ったジョーの視線がフランソワーズを射る。
「それはお前だっつってんだろ」
「うそ」
「嘘じゃねーよ」
「だって、知ってるもん。…この前見ちゃったもん。腕を組んで歩いてるの。長い髪の大人っぽいひとと」
「――いつの話だ」
「一週間くらい前」
「……ああ。あれか。ってお前、見てたのか」
「見たくなかったけどね。すっごいイチャイチャしてるのなんか」
今思い出しても胸の奥が真っ黒になっていく。
「あれは…なんでもない」
「あらそう」
「いや待て。だから違うって…あれはその。俺の姉貴みたいなもんでそんなんじゃ」
「あらそう」
「いやだから待てって。――その。プレゼント選ぶの手伝ってもらってただけで」
「……これ、そのひとが選んだものなの?」
「いやだから待てって。そうじゃない。俺が選んだ。ひとりで」
「だって手伝ってもらったんでしょ」
「いやだから。そのはずだったんだけど…」
ジョーの脳裏にユリとの一件がフラッシュバックする。
『だったらいいこと教えてあげる。その彼女はきっとこう言うわ。他の女性と一緒に選んだものなんか欲しくない、ってね』
だから自分で考えて悩んで、いっぱい彼女のことを思い出しながら――頑張って自力で選びなさい
そう言ってさっさと帰ってしまったのだった。
「――それは俺がひとりで選んで決めたから…」
ジョーが口のなかでもごもご言っている間にフランソワーズはそうっと包みを開けていた。
「…ふ。信じるわ。だってものすごく趣味悪い」
「悪かったな」
「ふふ」
「嫌だったら返せ」
「いやよ。気に入ったもの。だってこれ」
すごく可愛い。いったいどんな顔して買ったの?

それは約一ヶ月前の帰り道。
「もうすぐ12月かあ。早いよね」
「そうだな」
「テストがあって、それが終わったら球技大会があってあとは…」
「冬休み」
「もう。その前にクリスマスがあるでしょ」
「そして年越しだ。早いな」
「もう、その前に通知表貰うでしょ」
「興味ない」
「ジョーは何にも興味ないのね」
「そんなことない。興味はあるぞ。クリスマスとか」
「じゃあ一緒にいましょ。それでね、球技大会といえば…」
テストの後に行われる球技大会は生徒会の管轄だったのでフランソワーズの話はそちらにシフトしていった。
どうやら今はそれのことで頭がいっぱいなようだった。
だから。
あまりにもあっさりと交わした約束めいたことなど記憶にも残らなかったのだった。

「嫌な予感はしてたんだよな。この前、クリスマスはどうするのって訊いてきた時」
「もー。だったらその時そう言ってくれたらよかったじゃない」
「まさか完璧に忘れてるとは思わないだろ。仮にも委員長が」
「その呼び方やめて」
外で話しているのも寒いので――家の中に入り、リビングでコーヒーを飲みながら。
「でも…ジョー、楽しみにしててくれたんだ?」
「……まあな」
照れくさそうなジョーの顔を見る。が、目が合うと逸らしてしまう。ふたりっきりという状況に気持ちが追いついていかない。
「――それ、似合うな」
ジョーがフランソワーズの頭をつつく。
そこには彼がプレゼントしたカチューシャがあった。
リボンを模したデザインのカチューシャ。ベビーピンクの。
「ジョーのなかの私のイメージってこんな感じなの?」
「――さあな」
「でもどうしよう。私…」
振られたとばかり思っていたから、プレゼントなんて用意しなかった。
「別に要らねーよ。気にすんな」
「するよ。だってこんな可愛いの…凄く嬉しいのに。――あ、そうだ」
「ん?何――って、は、お前何……っ!!」
並んで座っていたソファ。膝がくっつくくらい近かったのに、ジョーが途端に身を引き距離をとった。一瞬の間に。
「きゅ、急に何を…っ」
「そんなに驚かなくたっていいじゃない」
「いやしかし」
「私からのクリスマスプレゼント。って、こんなんじゃ駄目?」
「だ」
駄目なわけ――ないだろっ!!
頬へのキスはジョーにとって忘れられないクリスマスプレゼントになった。
