|
今日はジョーの番、とテレビの前に陣取っていたフランソワーズは画面を見て呆然としていた。
「なによ、これっ……」
ジョーの登場だからと録画のセットもした。
そして、彼はいったいどんな一言メッセージを伝えるのだろうかと楽しみにしていたのだ。
ジョーに何度訊いても教えてもらえず、観てのお楽しみとはぐらかされてきた。
だから余計に楽しみだったのだ。
なのに、
「加速装置…って」
メッセージでもなんでもない。
更に言うと、朝の挨拶すら口にしていない。
「なんなのよ、これっ」
もっと言うと、画面からいなくなるなんて言語道断。残されたジェロニモが困っているではないか。
しかも、学生服を脱ぎ捨てている。何のためになのか必要性がわからない。
「――早着替えを見せたかったのかしら」
誰に?
視聴者に?
あるいはファンに?
フランソワーズが固まったままあれこれ検証していると、背後から抱き締められた。
「うるさいなぁ。ちゃんと最後は笑顔だろ?」
だからいいじゃないかと鼻をすりよせられた。
「ん……まあ、それは確かに……」
ジョーの笑顔は爽やかだったし、素敵でもあったので、フランソワーズはしぶしぶ頷いた。
悔しいけれど、ちょっとドキドキしてしまった。
見慣れているはずなのに、こうしてメディアを通すと違って見えるのはなぜなんだろう?
「だろ?……おはよ、フランソワーズ」
「おはよう、ジョー」
昨日、トモエに追い出されたフランソワーズがジョーのところへ行こうかどうしようか迷っていた時だった。
偶然、外を歩いていたジョーと行き会ったのだ。
そのまま当然のようにフランソワーズの部屋までくっついてやってきたジョーだった。
本人曰く「コンビニでも行こうと思って」歩いていたということだったが、手ぶらだったので――本当に偶然だったのかどうか真実は定かではない。
「…………」
「…………」
「…………」
「…………あの、ジョー?」
「――うん?」
「その、……離してくれる?」
「なぜ?」
「だって」
くすぐったいし。
ジョーにくっつかれていたら、朝食の支度もできない。
それに何より、落ち着かない。
「あの、朝御飯の」
「まだ腹減ってない」
「でも、その」
「いやだ」
ますますぎゅうっと抱き締められ、フランソワーズは諦めた。
ジョーがこうなったら、何を言ってもダメなのだ。頑固といえば頑固だし、わがままといえばわがままで、甘えんぼうといえば甘えんぼうなのである。しばらく好きにさせるしかない。
ジョーの気がすむまで。
「――フランソワーズ」
しばらくして、ジョーがフランソワーズの首に顔を寄せたまま言った。
「なあに?」
「今回の企画でわかったことがあるんだ」
「企画って、ZIPの?」
「うん」
「なにかしら」
「僕は毎朝フランソワーズに会いたいし、こうしたい、って」
フランソワーズは目を伏せた。
「フランソワーズは?」
「私?」
「うん」
どう思っているのと囁かれ、フランソワーズは小さく私もよと答えた。
「だったら、」
途端、笑顔になったジョーにフランソワーズも笑顔を返した。
「でもダメ。引っ越しはしないって言ったでしょ?」
「え、引っ越し?」
「もう、ダメよジョー。私はヒルズに住む身分じゃないの」
さあ朝御飯にしましょうと、フランソワーズはジョーの腕をあっさり解くとキッチンへ消えた。
リビングにはジョーひとりが残された。
「――ったく」
結局、フランソワーズの真意はわからない。
はぐらかしているのか、拒否なのか、あるいは本当にわかってないのか。
「いや……見てろよ」
サイボーグナンバー009は諦めが悪いのだ。
「何度だってトライするさ」
プロポーズだとわかってくれるまで。
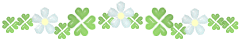
「わかってないのはジョーのほうよ」
キッチンでフランソワーズが呟いた。
|