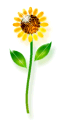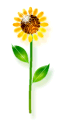|
「――あ。ダメだよ、ズルしたら」 迷路の入り口で、いままさにスキップして中に消えようとしていたフランソワーズの手首を慌てて掴む。 「だから、ちょっと待てって」 片手を挙げて宣誓する。 「フェアプレイの精神で頑張りまーす」
***
北海道にあるひまわり畑。 「3,2,1、スタート!」 勝手にカウントダウンすると迷路の中に消えていった。 ジョーは軽くため息をつくと、背の高いヒマワリを見上げた。 迷路とはいっても、簡単なもののはずだった。――が、聞けばそれは間違いで、軽く30分はかかるというシロモノだった。 「ふぅん。でも私は10分で抜けて見せるわ」 そう宣言し、闘志を燃やすフランソワーズ。 「目と耳を使わなくても、そういう空間感覚とか方向感覚には自信があるの」 全く自信のないジョーは、「一緒に行こうよ」と言いかけるのだが、 「003と009の勝負よっ!」 そうきっぱり宣言されては、従うしかないのだった。
***
案の定、迷った。
大体、僕はそういうのは担当していないんだ。リーダーだから指示は出すけれど、敵の情報とか、距離がどのくらいとか、そういうのは―― 隣で教えてくれる存在は必要不可欠だった。
自分で思っているより、頼ってたんだなぁ。
改めて思う。 でも。 ――守られていたのは、こっちのほうだったよ。 何しろ、こんな人造迷路でさえ、簡単に迷ってしまう。
「5メートル先を左に進んで」
ぐい、と手が引かれるのと同時に耳慣れた声がした。 「・・・フランソワーズ」 30分? 腕時計を見ると、確かに30分が経過しているようだった。 「ホラ。こっちよ」 手を引かれながら歩く。握り合った手は決して離さずに。 「本当に目は使ってないんだね」 嬉しそうなフランソワーズを見つめ、ジョーの顔にも笑みが浮かんでいた。 「でも、待っても待ってもジョーったら来ないんだもの」 ちらりと隣の彼を見つめ、 「――私がいないと」 そうして、両手で彼の手を包み込んだ。
|