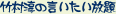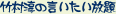|
丂傏偔偺儂乕儉丒儁乕僕偺乬挳偒傕偺俠俢乭偺棑偵徯夘偟偨僷儞僠儑僗偑傜傒偺2枃偵偮偄偰栤戣偑惗偠偨偺偱丄崱夞偼偦偺偙偲偵傆傟偨偄丅
丂偦偺1枃偵娭偟偰丄傏偔偼偙傫側晽偵彂偄偰偄傞丅
Charlie Zaa & Los Panchos"Romance de otra epoca"
偼偭偒傝尵偭偰丄偙偺儗僐乕僪偼嵓媆揑彜昳偩丅傕偲傕偲傆傢傆傢偲儘儅儞僥傿僢僋側壧傪塖偭偰丄傏偔偼偪偭偲傕岻偄偲偼巚傢側偄偑丄恖婥偺偁傞僐儘儞價傾偺庒庤壧庤僠儍乕儕乕丒僒乕偑忋婰偺傛偆側CD傪弌偟偨丅偍傑偊傕僷儞僠儑僗偐偲巚偭偨偑丄僷儞僠儑僗岲偒偑懡偄儔僕僆偺挳庢幰僒乕價僗偺偨傔偵偲攦偄媮傔偰挳偄偨偑丄洓傒偨偄側塖偵怱掙暊偑偨偭偨丅
丂慡12嬋偺偆偪1.3.4.6.7.9.10.12.偺8嬋偑幚懱偑偼偭偒傝偟側偄儘僗丒僷儞僠儑僗偺墘彞偱柺敀偔傕側傫偲傕側偄丅偙傟偱偼僆儕僕僫儖偺僷儞僠儑僗偵柍楃偩丅偦偟偰僒亅帺恎偑塖偆4嬋偵偟偰傕丄僾僄儖僩丒儕僐偺儀僯乕僩丒僨丒僿僗乕僗偺柤嬋乽傢偨偟偨偪偺惥偄乿偺僀儞僩儘偱僷儞僠儑僗偺墘憈傪巊偄丄搑拞偐傜嫮堷偵丄偟偨偑偭偰偒傢傔偰晄帺慠偵僆働偺敽憈偵戙偊傞側偳丄側傫偲傕傂偳偄丅偙傫側儗僐乕僪偼愨懳偍攦偄偵側傜側偄傛偆偵偲偛拤崘偟傑偡丅
丂偙傟偵偮偄偰偼側偵傕栤戣側偄偺偩偑丄傕偆1枃偺傎偆傕偙偺CD偲摨條偵嵓媆傑偑偄偺傾儖僶儉偩偲敾柧偟偨偺偩丅
Julito Rodriguez丒Johnny Albino丒Enrinque Caceres
"Homenje a El Trio Los Panchos丒El Reencuentro"
丂僩儕僆丒儘僗丒僷儞僠儑僗恖婥偼丄悐偊傞偳偙傠偐丄傑偡傑偡偦偺儃儖僥乕僕偑崅偔側偭偰偄傞傛偆偩丅儀僱僘僄儔偺"僄儖丒僾乕儅"偙偲儂僙丒儖僀僗丒儘僪儕僎僗偑丄僷儞僠儑僗偺墲擭偺柤墘彞偵帺暘偺儃僀僗傪偐傇偣偨乽嫟墘傾儖僶儉乿偑僸僢僩偟偰埲棃丄偦傫側孹岦偑嫮傑偭偰偄傞傛偆偩丅
丂杮嶌傕僷儞僠儑僗恖婥傪摉偰崬傫偱偺婇夋偩偑丄拞枴偼偄偄丅偦傟傕偦偺偼偢丄3戙栚偺僼儕乕僩丒儘僪儕僎僗丄5戙栚偺僕儑僯乕丒傾儖價僲丄6戙栚偺僄儞儕働丒僇僙儗僗偲丄僷儞僠儑僗偺楌戙僩僢僾丒儃僀僗偑堦摪偵夛偟偰夰偐偟偺僷儞僠儑僗偺僸僢僩傪塖偭偰偄傞偺偩偐傜丅3戙栚偑75嵨丄5戙栚偑82嵨丄6戙栚偑64嵨偱丄偲偙傠偵傛傝儓儗儖偲偙傠傕偁傞偑丄扨側傞僩僢僾丒儃僀僗偺摨憢夛偵廔傢傜偢丄偟偭偐傝塖偭偰抏偄偰枺椆偡傞偺偼偝偡偑偩丅偪側傒偵丄乽偁傞楒偺暔岅乿乽儁儖僪儞乿側偳5嬋傪11/7偺俹僌儔僼傿僥傿偱曻憲梊掕丅偤傂偛堦挳傪両
丂乬挳偒傕偺俠俢乭偺棑偵偼忋婰偺傛偆偵徯夘偟偨偺偩偑丄偠偮偼偄傠傫側栤戣傪偼傜傫偱偄偨偺偱丄掶惓傪偐偹偰偛曬崘偟偨偄丅
丂傑偢栤戣偼乽3戙栚偺僼儕乕僩丒儘僪儕僎僗丄5戙栚偺僕儑僯乕丒傾儖價僲丄6戙栚偺僄儞儕働丒僇僙儗僗偲丄僷儞僠儑僗偺楌戙僩僢僾丒儃僀僗偑夰偐偟偺僷儞僠儑僗偺僸僢僩傪塖偭偰偄傞乿偺偼帠幚偱偁傞偑丄乽堦摪偵夛偟偰乿偼塖偭偰偄側偐偭偨偙偲偑敾柧偟偨偙偲丅俠俢偺巇條傗夝愢偐傜丄傏偔偑憗偲偪傝偟偰偦偺傛偆偵巚偄崬傫偱偟傑偭偨偺偑丄娫堘偄偺傕偲偩偭偨傢偗偱偁傞丅
丂偠偮偼丄偙偺傾儖僶儉偐傜乽偁傞楒偺暔岅乿乽儁儖僪儞乿乽楒偺幏擮乿乽偮偨乿乽儁儖僼傿僨傿傾乿乽僔儞丒僂儞丒傾儌乕儖乿傪曻憲偱傕徯夘偟偨偑丄偦偺嵺僕儍働僢僩偵昞婰偝傟偰偄偨偮偓偺僨乕僞傪偁傢偣偰徯夘偟偨丅
*Primera guitarra y 3ra voz: Roque "El G焑rito" Lozada
*2da guitarra 倷2da voz: John Gonzalez
*Teclados: Noel Rodriguez y Tito Vicente
丂偱丄偐偗偨嬋偺戝敿偱儕乕僪丒儃乕僇儖傪偲偭偰偄傞偺偼丄82嵨偺僕儑僯乕丒傾儖價僲偱丄寢嬊僠儍儞偲惡偑弌偰偄傞偺偼斵偩偗側偺偱傾儖價僲偺僶乕僕儑儞傪傏偔偼慖傫偱偄偨傢偗偱偁傞丅偦偙偱懠偺擇恖偺惡偑暦偙偊側偄偙偲偵婥偯偔傋偒偩偭偨偑丄晄妎偵傕偦傟偑弌棃偢丄娫堘偭偨忣曬傪偍揱偊偟偨丅傓傠傫曻憲偺偁偲丄悢恖偺曽偐傜乽堦摪偵夛偟偰塖偭偰偼偄側偄乿偲偄偆僋儗乕儉偺偍曋傝傪偄偨偩偒丄傏偔偼俀廡屻偺曻憲偱偍榣傃偟偰掶惓偟偨丅偦偺偲偒丄側偐偺侾恖偺曽偑乽傾儖價僲偺僶僢僋傪柋傔偰偄傞偺偼堦弿偵枅擭棃擔偟偰偄傞僶儖僈僗孼掜偱偼側偄偐乿偲巜揈偟偰偙傜傟偨偙偲傕曬崘偟偨偑丄偦偺偲偒傕傏偔偼傑偩忋婰偺僨乕僞傪怣偠偰偄偰丄偦傫側偼偢偼側偄偲巚偆偲偮偗壛偊偨丅偦偺悢擔屻丄搶嫗悽揷扟嬫偵偍偡傑偄偺MK偝傫偐傜丄偙傫側偍曋傝傪偄偨偩偄偨丅
丂乽11/7 (壩) 曻憲偺"Homenje a El Trio Los Panchos" 偺俠俢偐傜偺俇嬋偵偮偄偰巹埲奜偐傜傕斀嬁偑偁偭偨傛偆偱偡偹丅崱夞偺曻憲偱掶惓偝傟偰偍傝傑偟偨偑丄娫堘偭偨応崌捈偪偵掶惓偝傟傞偙偲偼戝曄尓嫊偱棫攈側懺搙偲姶怱偄偨偟傑偟偨丅側偍丄偁偺Johnny Albino偑壧偭偨俇嬋偼 Taulino Y Gabriel Vargas 偺敽憈偩偲偄偆曋傝傕偁偭偨偲曻憲偝傟傑偟偨丅巹傕16嬋傪柍堄幆偱挳偄偨抜奒偱 Julito Rodriguez偲Enrinque Caceres偺敽憈偑 requinto, guitarra, teclados 側偺偵丄Johnny Albino偺傕偺偩偗偑 requinto, gui- tarra, maracas 側偺偼偪傚偭偲傊傫偩側偀偲巚偭偰偍傝傑偟偨丅偙偺曻憲傪挳偄偰憗懍 "Homenje a El Trio Los Panchos" 偺俠俢偲97/11/21敪攧偺"Trio Los Panchos Best Album" (擔杮僋儔僂儞 CRCI-20323) 偺俠俢 (墘憈幰Johnny Albino, Taulino Y Gabriel Vargas) 傪怲廳偐偮柸枾偵挳偒挷傋偰傒傑偟偨丅偦偺寢壥俇嬋偲傕慡偔摨偠榐壒偱偟偨丅偄偢傟傕墘憈帪娫丄墘憈曽朄 ("Historia de un Amor"偱偺Requinto偺暊傪扏偔憈朄傗偦偺帪娫媦傃夞悢/僗僞乕僩19昩帪揰,38昩,55昩,57昩, "Obsecion"偱偺妡偗惡 1暘30昩帪揰摍丄摿挜揑側墘憈曽朄) 偑俇嬋偲傕摨堦偱偟偨偺偱娫堘偄側偄偲妋怣偟傑偟偨丅偍偦傜偔擔杮僋儔僂儞 (姅) 偐傜攦偄庢偭偰曇廤偟偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅乿
丂偙偺偍曋傝傪偄偨偩偄偰丄傏偔偼嬄揤偟偨丅側偤側傜丄忋婰偺僨乕僞偼恀偭愒側塕偲偄偆偙偲偵側傞偐傜偱偁傞丅偙偺傇傫偩偲丄俵俲偝傫偑彂偄偰偍傜傟傞傛偆偵丄乽擔杮僋儔僂儞 (姅) 偐傜攦偄庢偭偰曇廤偟偨偺偱偼乿偲偄偆揰傕夦偟偄傕偺偱偁傞偑丄偦傟偼傏偔偵偼娭學側偄偙偲側偺偱丄偙傟埲忋捛媮偡傞偮傕傝偼側偄丅偩偑丄側傫偲偟偰傕尵偭偰偍偒偨偄偺偼丄僄僌僛僋僥傿僽丒僾儘僨儏乕僒乕偲偟偰柤慜傪弌偟偰偄傞 Jorge Flores傕儈儏乕僕僇儖丒 僾儘僨儏乕僒乕偺Noel Rodriguez傕丄戝偺僀儞僠僉栰榊偵側傞偲尵偆偙偲偩丅偝傜偵尵偊偽丄偙傫側偄偄壛尭側傾儖僶儉傪暯婥偱儕儕乕僗偡傞BMG US LATIN偺恄宱傕媈傢偞傞傪摼側偄丅偦傟偵偟偰傕僷儞僠儑僗偑傜傒側傜攧傟傞偲偄偆壒妝僼傽儞偺怱忣傪怘偄暔偵偡傞僾儘僨儏乕僒乕偑偽偭偙偡傞嶐崱丄僷儞僠儑僗偑傜傒偺傾儖僶儉傪攦偆偲偒偼梫拲堄偱偁傞丅偲傕偁傟丄偙傫側僀儞僠僉俠俢傪徯夘偟偨偙偲傪抪偠傞偲偲傕偵丄偙傫側嵓媆巘揑僾儘僨儏乕僒乕偵嵭偄偁傟丄偲惡傪戝偵偟偰嫨傃偨偄丅
|