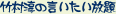

| 2001年11月23日「ラテン音楽のディーバ、クリスティーナ三田の唄に魅せられて」 |
|
さる10月29日のこと、ジョニー・アルビノ率いるロス・パンチョスを観に大宮まで痛む足を引きずっていった。9月末から持病の腰痛がまた発症し、痛みがいっこうに引かない。そのためいま一つ気乗りうすだったが、どうしてもジョニー・アルビノに会って確かめたいことがあり、遠路はるばる駆けつけたのだ。というのも、10月9日の放送でジョニー・アルビノの珍しいタンゴ・アルバムを友人のHさんから拝借して放送したところ大きな反響があった。その内容の素晴らしさといったら、アルビノの数多いアルバムのなかでも間違いなくベスト3にランクされる内容である。かってパンチョスを離脱した後アルビノが設立したSTABRIGHTというレコード会社からリリースしたLPがごく少し輸入されただけで、日本でのリリースはなく、またCD化もいまだに実現していない。それだけにその存在すら知らなかった人たちが多く、放送を聴いてレコード店に駆けつけた人が相当いたらしい。結局要領を得ないままNHKに問い合わせが殺到という事態になったのだ。で、その発売権を持っているのはだれか、いったいいつどこで録音したのか、といったことを知りたくてコンサート開始前に楽屋にジョニーを訪ねて話を聞いた。
仕事でアルゼンチンへ行ったところ、ペロン大統領の死に遭遇し、公演はキャンセルの連続でひどい目にあったという。そのどさくさに録音したアルバムだというので、歴史年表をひもといたら、ペロンは74年7月1日に他界しているので、どうやら74年の7月か8月頃の録音らしいことが判った。 談笑後、少々時間があったので劇場近くの居酒屋で軽く一杯やって、開演間際にすべり込んだ。心地よい演唱とほろ酔い気分が巧い具合に作用し、ウトウトしながら夢と現実の間をさまようことしばし。これぞ至福のときである。余談だが演唱が素晴らしすぎても、逆に下手でもそうはいかないから不思議である。 ともあれ、ぼくなりに今のパンチョスを楽しんでいたわけだが、そんなぼくが居住まいをただして聞き入ったのは、ゲストで登場したクリスティーナ三田が唄い始めたときだった。「エル・パストール」、そして「麗しのハリスコ」の2曲だけだったが、彼女の唄は完膚無きまでにぼくの魂を震わせた。足かけ21年もラテン音楽のDJをやっていながら、これまで彼女の素晴らしさを知らなかったことが悔しかった。とはいえ、この人の存在を全く知らなかったわけではない。98年4月末まで10年余ぼくが事務所をかまえていた四谷の坂町の近くに彼女が一時開いていたライブハウスがあり、そこの掲示窓に「クリスティーナ三田」と大書してあったので名前は覚えていた。それに一昨年7月、新宿厚生年金会館でロス・パンチョスの公演を観たときに彼女の唄も聴いてはいた。そのときはヤマトというデュエットでゲスト参加して唄ったのだが、なぜかその印象は希薄で、唄った曲すら思い出せない。なのに1年ちょっと経ってソロで唄ったクリスティーナ三田の唄に衝撃的ともいえるほどの感銘を受けたのはいったいなぜなのだろうか。いや、当夜彼女の唄にしびれたのはぼくだけでなく、音楽評論活動をしているHさんや彼の友人で在メヒコながらたまたま帰省中だったT氏も称賛。そのT氏にいたってはクリスティーナは絶対メキシコ人の血をひいているとまで言い出す始末。NHK宛にも当夜のショーを観た数人のかたからパンチョスよりも彼女のほうがよかったという感想をいただいた。もっと彼女の唄を聴きたいと書いてこられたかたもいた。その思いはぼくも同じだった。そこでトリオ・ペペスの菊池明さんに連絡して三田さんから電話をもらえるように計らってもらい、その結果11月14日に銀座にあるシグナスというジャズ・クラブで聴けることになったのだが、その夜を境にぼくのクリスティーナ中毒症状はさらに深まることになった。 腐ってもタイと言っては失礼かも知れないが、ジョニー・アルビノ率いるパンチョスとてやはりパンチョスである。そのバルガス兄弟の伴奏で唄うにあたって、かなりのプレッシャーがあったと思うが、それをはねのけて臆することなく唄った彼女の歌手魂にぼくには舌を巻いた。古くはミゲル・アセベス・メヒアの名唱があり、ロス・トレス・カバジェーロス、マリーア・デ・ルールデス、最近でもアイダ・クエバスらが心に残る名唱を残している名曲だが、あの夜大宮のステージで彼女が披露してみせた「エル・パストール」はそれらの列に加えられるべき一世一代の名唱だったとぼくは確信する。ペペスの菊池さんによれば彼女が十八番にしている曲だそうだ。シグナスのステージでも唄ったが、大宮で感じられた気迫こそなかったものの、歌唱そのものは素晴らしく、そのことはシグナスでご本人からいただいた92年録音のアルバムに入っている同じ曲についても言える。 クリスティーナ三田の魅力はなんといってもその落ち着きのある天性の美声にあると思う。透明感があり、よく伸びてよく通るハリのある声そのものが聴く者の心を惹きつけずにはおかない強烈な魔力を秘めている。裏声を巧みにまじえるというより、おそらく自然にファルセットになってしまうあの声は彼女の最高の武器になっているのではないか。 ブラジルでは歌手をカントーラ(歌い手)とイテルプレタ(表現する人)にわけることが多いが、クリスティーナ三田はあきらかに後者。その歌があるべき理想の姿を自分のなかで飽くことなく追求し、歌に命を吹き込むのだ。きっと計算しつくされたであろうに、それを全く感じさせない。むしろひたむきで、けなげな感じすらする情感の表出がまた素晴らしい。自分を甘やかさず聴き手にも媚びることのない、凛として気品のある歌唱はほとんど完璧といってもいい。レパートリーの豊富なことも彼女の強みである。シグナスでは3ステージを聴いたが、お客からリクエストをもらいながら、「できるかしら?もう長いことやってないから...」などと言いつつ、「青い月影」や「エル・チョクロ」をあざやかに唄いこなしてしまうのを目の当たりにした。それでいて歌詞も正確なら、つぼを心得た唄いっぷりも見事だった。 そんなラテン音楽のディーバとの邂逅にぼくの心はときめいている。これまでキューバで3枚のアルバムをプロデュースしてきたが、できればクリスティーナ三田をメキシコに誘ってその類稀な魅力を十二分にとらえたアルバムをプロデュースしてみたいとも思う。マリアッチ〜トリオ〜ギターだけの伴奏(本人の弾き語りかアントニオ・ブリビエスカのような達人のギター伴奏)といった様ざまなフォーマットで録音すれば、いま最上の状態にある彼女の唄をアルバムに収録できるような気がしている昨今である。 写真は「注目のアーティスト」ページをご覧ください。 |
「竹村淳の言いたい放題」目次へ
| ホーム | インフォメーション | 聞きものCD | ミュージック・プラザ | 注目のアーティスト | ラテン音楽ベスト100|