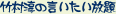

| 2002年3月28日 ポップス・グラフィティのご愛聴に感謝! 新番組ミュージック・プラザに乞うご期待。 |
| 1996年4月から始まったNHK-FMの番組ポップス・グラフィティがこの3月末で終了となった。満6年の歳月が流れたわけだが、アッと言う間だった。そもそもぼくがNHK-FMと関わりを持つようになったのは1979年からで、そのときはDJとしてではなく、当時の人気番組クロスオーバー・イレブンにライターとして起用された。紹介者は同番組でライターとして好評を博していた西尾忠久さんである。氏は世界の一流品をテーマに健筆をふるった方だが、それ以前はコピーライターとして活躍。また世界の広告研究などでも知られた人なので、ご存知の方も多いと思う。 そして1980年の年末のこと、現ラティーナ誌のオーナー編集長である本田健治氏の紹介でオーディションを受け、当時谷川越二氏がDJを担当しておられた世界の音楽〜中南米の旅の後続DJに迎えられることになった。それは81年4月のことだったから、この3月で満21年が経過したことになる。ただし85年4月〜87年3月の2年間はピアニストの松岡直也氏がNHK-FMのラテン音楽のレギュラーDJを担当し、ぼくはイレギュラーで年2回ほどの出演だったから、厳密に言えば満19年の間、NHK-FMラテン音楽番組の選曲・構成・トークを独りで担当してきたことになる。いずれにしても記録的な長丁場であることには変わりなく、よくぞ続けてこられたというのが偽りのない実感である。 20世紀が終わる2000年度でおそらくぼくのDJ生活も終了することになるだろうという読みで、1999年5月から「竹村 淳のトークとお勧めライブ」という企画をスタートさせた。ラジオでは顔が見えないし、現役のうちにリスナーの方がたと直接お目にかかって長年ぼくをサポートしてきてくださった皆さんとお会いしておきたかったからである。 東京恵比寿でメキシコ料理店をやっている歌手のサム・モレーノさんの協力を得て、ブラジル出身の女性歌手ヴィウマさんをゲストに迎えて第1回の集いを開催したのが99年5月だった。当初は2001年3月までに東京で6回開催して、それとは別に地方にも何回か出かけて行き、そして放送終了とともにその企画も終了させるつもりでいた。ところが、ポップス・グラフィティはこの3月まで続き、「竹村 淳のトークとお勧めライブ」のほうも東京で年2回、地方で3回開催した。そして大勢のリスナーとお目にかかり、いろいろとお話を聴けたのは本当に素晴らしい体験だった。 ポップス・グラフィティが2002年3月末で終了すると聴いたとき、ぼくはもうお役ゴメンと思ったのに、続投を打診されたとき、内心ぼくは戸惑った。というのも、昨年末に坐骨神経痛にかかり、体力的に自信満々ではなかったからである。散々迷った末に、頑張るぞと自分に言い聞かせ、いよいよ4月2日(火)午後4時から新番組ミュージック・プラザにのぞむことになる。この6年間、励ましや感謝のお便りやメールをくださった大勢の方がたには心からお礼を申し上げます。またお叱りやご教示をくださった方がたにも感謝申し上げます。長年慣れ親しんできた服部克久さん作・演奏のテーマ曲ともお別れである。 新番組ではそれぞれのDJが自分の担当時間のテーマ曲を選ぶこととなり、ぼくは3曲選んだので、いち早く本欄の読者諸氏にご報告しておきたい。 *オープニング・テーマ:エンリケ・チア(p)の「カチータ」 *中間テーマ:ルス・マリア・ボバディージャ(g)の「ビジャンシーコ」 *エンド・テーマ:ルシア塩満(arpa)の「遠いあなたへ」 それでは、皆さん、4月からはNHK-FMの火曜日午後4時のミュージック・プラザ第2部ポップス〜中南米とカリブ編でお耳にかかります! |
「竹村淳の言いたい放題」目次へ
| ホーム | インフォメーション | 注目のアーティスト | 聞きものCD | ミュージック・プラザ | ラテン音楽ベスト100 |