「ひとりで平気」
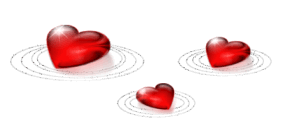
君は強いひとだから、ひとりで平気だよね? そう言われたから、私はそうねと答えるしかなかった。 そうして見送った背中。 きっと彼は、彼がいなくては夜も昼も明けないような弱い子がいいのだろう。 *** 「ふうん。・・・まぁ、多少複雑な気持ちにはなるけれど、僕としては良い話を聞いた」 「その見る目の無い奴が君を振ってくれなかったら、今でもソイツと付き合っていたかもしれないんだろう?」 そんなことないわ、と言いかけたけれど、ジョーは構わず続けた。 「振ってくれて感謝・・・と言いたいところだけど、問題はフランソワーズだ」 私が答えず笑っていると、ジョーは回している腕に力を込めて引き寄せた。 「酷いなあ、一緒にしないでくれよ。確かにきみは強いひとではあるけれど」 そうしてジョーは私の耳元に唇を寄せた。 ・・・独りが平気なわけじゃないだろう? ちゅ。と首筋にキスをしてから、ジョーは顔を起こした。 「昔の話だから、妬かないけどさ。・・・やっぱりすっきりしないな」 鼻にかかった甘えるような声。 「ジョーったら。あんなひと、もう顔も覚えてないわ」 私が強いひとだと知っても、あなたは私を独りにしない。 意味がわからない。 「だから。きみは綺麗だから、ひとりにしたら大変だってこと」
私は確かにそういうタイプではないから、本当に頷くしかなかったのだ。
私はなぜこんな話になったのだろうと思いながら、背後から肩に顎を載せてくるジョーの頭を撫でた。
「私?」
「ああ。見る目がなさすぎる」
「そうね。昔から、男のひとを見る目がないのかも」
「あれ?それってもしかして僕も含まれてる?」
「ホントかなぁ」
「本当よ。・・・だって」
しなかった。
「うーん。僕だったらこう言うな」
「なあに?」
「きみは綺麗だからひとりで平気なわけないだろう」
「・・・ん?」
いつもついていなくちゃねと言ってジョーは私を抱き締めた。
![]()