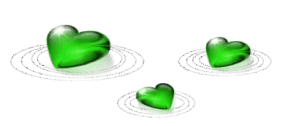
「続・黒と蒼」
辛いなら、やめてしまえばいい。
一緒に逃げよう。
――そう、彼女は言った。
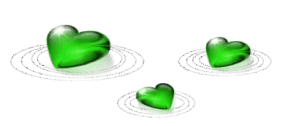
その頃の僕は、F1のシートを獲得できるか否かの瀬戸際だった。
僕の持てるもの全てを賭けたといってもいい。
できることなら、なんでもやった。
綺麗なことも、汚いことも。
今までいいことなんか何一つなかった。
そんな僕の、たったひとつの取り得は反射神経がいいことと動体視力が優れていることだった。
だから、ケンカは強かった。
なにしろ、相手のパンチも蹴りも入らない。
全て見えてしまうのだから、よけるのは造作もないことだった。
車が好きだった僕は、早くからドライバーになることを夢見ていた。
自分の取り得が優れていることもわかっていたから、あとは運転テクニックだけだと思っていた。
そしてそれは当たっていて――僕はどんどんのし上がっていったのだ。
あと数戦で決まる。
全てのレースで表彰台を獲得すれば、僕は来季からF1パイロットになれる。
そんな時期だった。
***
僕はまだまだ無名だったけれど、それでも勝利を重ねていけば、それなりに名前を知られるようになり、レースファンの間で囁かれるくらいにはなっていた。
そんな僕に、ファンができた。
少し年上の、モータースポーツ好きの女性。
名前はマユミ。
マユミさんは、僕が連勝する前からサーキットに通っていて、他のドライバーの話によれば、ともかく車が好きなのだという。
特に誰のファンということもなくサーキットに通う女性ファンは珍しかったから、僕はだんだん気になってきた。
いったいどんなひとなんだろうと。
単純に、どんな物好きなんだろうと思っただけだったかもしれない。
ともかく、その女性に興味が湧いた。
注意して周りに目を向ければ、確かにマユミさんはいつもサーキットにいた。
特に誰かを応援しているという風でもなく。
顔を合わせるようになれば、自然に知り合いにはなる。すれ違うときは、軽く会釈を交わすくらいには。
でも、全然話したこともなかった。
ただ、彼女が応援するのはどんなドライバーなのだろうと、彼女のおめがねに叶うのは誰なのだろうとそう思っていた。
今思えば、それが僕の初恋だったのだろう。
![]()
![]()
![]()
その日は、小雨の降る少し肌寒い日だった。
僕のレースがあった。
多少、緊張はしていたものの、自信はあった。
負ける気は全くなかったし、それに――あと少しで、僕の夢に近付くことができるのだ。
僕には失うものなどなにもない。今までのように、この身ひとつでやっていくだけだ。
――飢えたような瞳。
よくそう言われたものだった。
そう――おそらく僕は飢えていたのだろう。あらゆるものに。
そして、僕が持っていないそれらをさも当然のように持っていながら気付いていない奴らを嫌悪していた。
それがいつも顔に出ていたのだろう。
僕は、嫌われ者だった。
そんな僕が優勝した。
もちろん、チームメカニックは喜んでくれた。でも、他のチームからは散々陰口をたたかれた。
いったいどんな手を使ったのだろうとか、金をばら撒いて勝ち取った勝利なのだろうとか。
僕にばら撒くような金などあるはずもないのに。
優勝カップを掲げたとき、僕の首筋に抱きついてきた者がいた。
そんな風に勝利の喜びを表現してくれた者はいなかったから、僕はあやうくカップを落とすところだった。
だってそれは――マユミさんだったのだから。
「ジョー!おめでとう!」
***
それがきっかけで、僕とマユミさんは急速に仲良くなっていった。
サーキットにいる時も、そうでない時も、一緒にいるようになった。
「マユミさんは、最初から僕のことを見ててくれたんですか?」
「えっ・・・うふ、そうね」
「あ、イヤだなぁ。そういう思わせぶりな感じ」
「そう?――だって、ジョーったら全然自信を持ってないんだもの」
「自信?」
「そうよ。あなたってとても魅力的なのに。もっと自分に自信を持ってちょうだい」
そう言って笑った。
黒い瞳が煌いて、僕はそれを見るのが嬉しくて楽しくて――毎日が幸せだった。
でも、その幸せは長くは続かなかった。
マユミさんと付き合った頃から、僕の成績は落ちていった。
チームからは、もちろん叱られた。もっと集中しろと何度も言われた。
僕自身は、レースに全てを賭けていたから、そう注意されても何がいけないのかさっぱりわからなかった。
ただ、勝てなくなったことだけは確かで、このままではとてもF1には届きそうになかった。
今まで、世話になってきたチーム。
僕に賭けてくれたひとたち。
出世払いでいいと笑ってくれたひとびと。
彼らの顔が脳裏をよぎる。
僕は負けるわけにはいかない。
だけど、今の成績のままではとても――届かない。
あと2戦。
表彰台だけではとても足りない。2戦連続で優勝できなければ、夢は水泡に帰す。
F1パイロットになるのは、既に僕だけの夢ではなくなっていた。
僕を信じて支えてくれたひとたち全ての夢であり、そして誰よりも一番近くで応援してくれるマユミさんの夢でもあった。
だけど。
今のままの僕ではその夢には届かない。
![]()
![]()
![]()
レース前、僕は随分とナーバスになって、大好きなマユミさんにも辛くあたってしまった。
でも、彼女はそんな僕をなじることもなく、じっと黙っていてくれた。
そして、暴れて喚いて、頭を抱えて静かになった僕に言ったのだ。
「そんなに辛いなら、やめちゃえばいいのよ。今までお世話になったひとたちへの恩とか、そういうものが重いのなら・・・逃げてしまえばいい」
「えっ?」
「ジョー。一緒に逃げましょう。このまま」
何を言っているのかわからなかった。
「だって、ジョーが辛い思いをしているのを見るのは辛いわ」
「・・・だけど、マユミさんだって僕が勝つのを見たいって・・・」
「そういったけれど、こんなに辛いなんて思わなかったもの。ね?何もかも捨てて、逃げてしまいましょう」
僕は何も言えず、ただマユミさんの顔を見ていた。
彼女が僕を抱き締めても、ただ――ぼうっとしているだけだった。
何もかも捨てて。
仲間も。
マシンも。
僕の夢も。
全部――捨てて。
逃げる。
・・・どこ、へ?
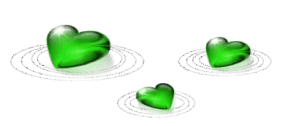
そんな僕の弱い部分に嫌気がさしたのだろう。
それからほどなくしてマユミさんは僕の前から姿を消した。
サーキットにも来なくなった。
![]()
![]()
![]()
そのあと、僕は逃げも隠れもせずレースに出て連勝し、晴れてF1パイロットとなった。
マユミさんは、どこでどうしているのか。
誰も知らなかったけれど、口さがない者たちの噂では、彼女は将来有望なドライバーを物色していただけなのだろうということだった。
本当かどうかは知らない。
今となっては、確認する術もない。
だけど、僕は――たとえそうでも、マユミさんを憎む気持ちにはなれなかった。
僕の初恋のひとに間違いはなかったのだから。
いつか、また会うことがあったら。
その時は。
――その時は。
僕は何と言うだろう?