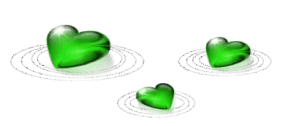
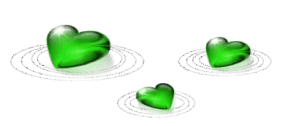
全くしょうがないんだから、という声を背中に受けながら部屋に向かった。
きみにぐいぐい背中を押されて。
思えば長い一日だった。
博士に聞いたのだけど、僕とスクナとの戦いの様子はずっと監視カメラで観察されていたのだという。
そして、フランソワーズも一緒に見ていた。成り行き上、見ないわけにはいかなかったらしい。
彼女は見ていた。ずっと。僕が負傷していく姿を。
仲間の誰が負傷するのでも心配するきみにとって、それは辛い事だっただろう。
確かに僕もあの一瞬、死を覚悟した。
――イワンが起きなかったら、おそらく死んでいた。
そう思うと、本当に指名されたのがきみじゃなくて良かったと心から思う。
もしそれがきみだったら。
そう思うと背筋が寒くなる。
が。
もしきみだったとしても、僕はきみを行かせたりなんかしなかったから同じかな。
部屋に着いてからも、彼女は忙しく動き、さっさと僕を寝かしつけようとした。
いくら「大丈夫」といってもきかない。
可愛いフランソワーズ。
左腕しか使えないのがもどかしい。
こんな状態では、彼女をつかまえられない。
抱きしめることもできない。
あとは自分でするからとベッドに座った僕を振り返り、彼女はにっこり微笑んだ。
そうして僕のそばに来て「おやすみなさい」と額にキスをした。いつものように。
でも、行かせない。
今日はまだ、そばにいて欲しい。
だから、僕は使える左腕を伸ばし彼女の肩を抱きしめた。
フランソワーズは一瞬、驚いて――そのあと、ゆっくりと僕の肩から腕を回して僕を抱きしめた。