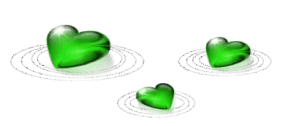
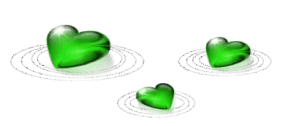
いま、僕の腕の中にきみがいる。
膝の上に座って、僕の胸にもたれている。
・・・鼓動が速くなる。
きみはいつも優しい。
僕の手を振り払わない。
僕が触れても嫌がらない。
僕がキスしても逃げない。
だから僕は勝手に思っている。
きみも僕を好きなのに違いないと。
僕がきみを好きなように。
でも、それはやはり勝手な思いであり、僕はいつも不安になる。
きみはいつも優しいけれど、その優しさは僕だけに向けられている訳じゃない。
仲間の誰が怪我をしても、等しく与えられる優しさだ。
別に僕だけが特別な訳ではない。
きみは誰にでも優しい。
だから。
きみは誰の手も振り払わない。
だから。
仲間の誰が触れても嫌がらなくて、誰がキスしても逃げない・・・のかも、しれない。
――誰がキスしても。
嫌だ。
そんなの、嫌だ。
他の誰かとキスするきみなんて、想像もしたくない。
でも。
僕は日本人だから慣れていないだけで・・・他のみんなにとっては、日常のごく当たり前の事なのかもしれない。
だから、もしかしたら。
きみは他のみんなとも――そうしているのかもしれない。
腕の中にきみがいても、いつもいつも不安になる。
どうして僕は、こんなにきみが好きなんだろう。
きみは僕を嫌がらないけれど、だったら僕のことを特別に思ってくれているのかというとそうではない。
平等。
他の誰とも差のない僕。
じわり。と胸に広がる黒い想い。
――これは嫉妬だ。
彼女が優しくするもの全てへの。
僕に彼女が与えてくれる優しさを等しく享受する者への。
僕だけを見ていてくれたらいいのにな。
僕のことを好きになってくれたらいいのに。
そうしたら、僕はきっと今までよりももっと強くなって、誰にも負けない。
そしてきみを守る。
そして、もっともっときみのことを好きになる。
だって、我慢しなくてもいいだろう?きみを好きだという想いを。
――いや。
違う。
きみが僕のことを好きにならなくても。
僕はやっぱり、きみのことをもっともっと好きになっていく。
いまこの時だって、一秒経つごとにきみをもっと好きになっていく。
ほら。
一秒前の僕より、今の僕の方がきみを好きな気持ちが強くなっている。
きみはいま、僕の腕の中で誰を想っている?
僕の知らない誰かのことだろうか。
――僕のことだったら、いいのに。