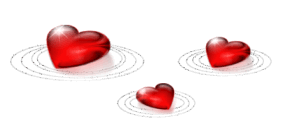
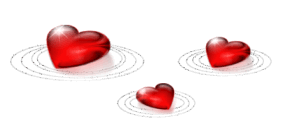
気付いた時には、もうすっぽりとジョーの腕のなかにおさまっていた。
ジョーの膝の上で、子供みたいに抱っこされている。
・・・どうしよう。
顔を上げられない。
ジョーの顔を見られない。
だって私、きっと真っ赤になっているから。
心臓がどきどきして、ジョーに聞こえてしまうかもしれない。
こういう時、ああ慣れているんだな・・・って思って、ちょっと寂しくなる。
他の女の子にもきっとこうしているんだなぁって。
そして、胸の奥にトゲが刺さったみたいに苦しくなる。
ジョーが見つめる女の子。
ジョーを見つめる女の子たち。
みんなまっすぐな目で「あなたが大好き」って言ってるのがわかる。
きっと彼にもわかっている。
――私は素直じゃないから、そんな目で彼を見ない。
「仲間」だから、そういう目で彼を見たりなんか、しない。
だから、他の女の子を守る彼を見ても、何も思ってはいけないの。
優しい瞳で彼女たちを気遣い、庇う姿。
何気なく回された腕。甘い声で無事を確かめて。
ジョーが他の女の子の名前を呼ぶのなんか、何度も聞いている。
だから、もういい加減に慣れてもいいのに――いつまで経っても、慣れない。
耳のスイッチをいれなくても聞こえてしまう、あなたの声。
すぐに聞き分けてしまう、あなたの声。
あなたが気にかけているのは、いつも私だけではない他の誰か。
私があなたに守られるのは「003」としてあなたに必要とされている時だけ。
「フランソワーズ」としてではない。
そんな時、私はちょっと意地悪になる。その「誰か」に対してこう言ってしまう。
ジョーが優しいのは、あなたのことが好きだからじゃないのよ。
彼は誰にでも優しいの。
――でも。
そう言い放った瞬間に、その言葉は私に向かって返ってくる。刃となって私の胸を刺す。
ジョーが優しいのは、私のことが好きだからじゃないのよ。
彼は誰にでも優しいのだから。
――わかってる。
そんな事は、ずうっと前から知っている。
だから私は「003」として彼の隣に立つ。
あなたが誰を好きでもいい。
私はあなたが好きだから、大事だから、だから――守りたいの。
それは他の女の子にはできない「003」である私だけの特権。
あなたが守りたいと思うものを、私も守る。
そして――大事なあなたも、私が守る。
他のどんな女の子にもできない、私だけの特権。