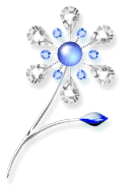
「鋼鉄の体」
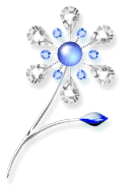
鋼鉄の体。
何年前になるだろう。黒い瞳の彼女にそう言われたのは。
改めて口にされた時はショックだったけれど、いまこうして落ち着いて考えてみると、彼女はただ事実を述べただけに過ぎなかったのだろうと思う。
彼女たちから見れば、体が機械の僕らなど同じ人間だとは到底思えないだろう。
ケガをすればそれなりに痛いし、ダメージも受ける。
が、血は流れない。
ただ穴が開くだけだ。
僕は他の者より特にそうで、何しろ90%近くが機械の体だ。
たぶん、脳の他は本当に一部を残してあとは生身ではないのだろう。
これが、例えば脳だけ無事で、あとは機械にしなければ助からなかったという「治療」ならばまだ納得がいっただろう。
しかし、これは「治療」ではなく「実験」だった。
どこも悪くないのにメスを入れられ、体の中身をそっくり抜き取られ替えられた。
外から見るぶんにはわからないだろう。
博士によれば、X線を通しても普通の骨格が写るような処理がなされているという。
完璧だった。
飛行機に乗るのにも全く問題はなくて、自分の体内のものが金属探知機にひっかかることもない。
だから、――実は、サイボーグではないのではないか・・・と思ってしまいそうになる。
でも、そうではない。
僕たちは。
僕は。
鋼鉄の体を持っている。
おそらく、忘れてもいいのだろう。自分が遭った運命なぞ。
現に、いまもこうして難なく普通の生活を送れているのだから。
――でも。
鋼鉄の体。
あの時、投げつけられた言葉は僕のなかに今でも留まっている。
沈殿して表面上は見えなくなっても、それでも少しかき混ぜれば簡単に浮かび上がってくる言葉。
僕の鋼鉄の体で生身の自分らを守れと彼女は言った。
そうでなければ会いに来たりしなかった。そうも言った。
あの時の彼女にとって僕の価値は鋼鉄の体を持っているというそれだけだった。
僕の中身などどうでもよかったのだ。
僕が何を考え、何を思い、どんな過去を持っていま生きているのかなぞどうでも良かったのだ。
ただの――道具だった。
ただの道具に成り果て、砂漠で散るはずだったこの僕を救ってくれたのはフランソワーズだった。
彼女は。
僕が何を考え、何を思い、どんな過去を持っていま生きているのかを知って、そしてそれが大事だと言う。
過去だけではなく、未来も大事にしようねと言う。一緒にいるから、と。
未来。
僕にはそんなもの、考えても無駄だと思っていた。
今まで生きてきて考えたこともない。
望んだって夢見たって、絶対に――叶わないのだから。
しかし、そんな僕に彼女は言うのだ。
一緒に未来を見つめよう、と。
鋼鉄の体を持たなければ、フランソワーズと出会う事もなかっただろう。
いうなれば、生身の体と引き換えに僕はフランソワーズと出会った――と、そういうことになるのだろう。
――だったら。
鋼鉄の体もそんなに捨てたもんじゃない。