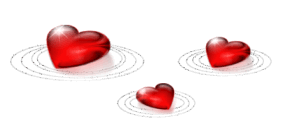
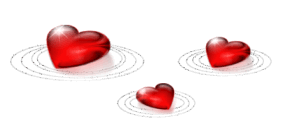
一回、小さく頷いて。
「そういう日があってもいいと思うの。・・・あってもいいのよ」
僕は声もなくフランソワーズを見つめていた。
・・・僕は、何を遠回りしていたのだろう。
僕が探していた答えは彼女が持っていた。
いつもそばにいた彼女が。
「自由な自分」になるためには、自分のことを知らない人の中に身を置くしかないと思っていた。
僕がサイボーグであることを知らない人たちの中に。
でも、実際は。
雑踏の中に身を置いても、孤独感が増すだけだった。
「王女さまのこと、好きだった?」
「・・・うん」
「そう。・・・会えて、嬉しかった?」
「・・・うん」
「そう。」
そう言って、僕の腕にもたれる。
「・・・ちょっと妬いちゃった」
え?
「・・・ちょっとだけ、よ」
「・・・妬くことなんてないのに」
「ん・・・そうなんだけど」
答えたフランソワーズの声が揺れた気がして、顔を覗きこむ。
「・・・フランソワーズ?」
![]()
一瞬、滲んだ涙を、睫毛の下に隠すように目を閉じる。
泣いたらジョーが困るから。
ジョーが王女様に心を移していたのは事実だった。
もう終わった事よ、フランソワーズ。
そう言い聞かせても、心は波立ったまま。
さっき、グレートにあたってしまった事も後悔しているのに。
妬いて、誰かにあたるなんて、そんな自分は嫌い。
あなたに、見せたくなかった。
・・・だけど。
本当は、もうあなたは戻って来ないのではないかと思っていた。
いつもあなたの心は、どこか遠くに行ってしまっていて。
私の事は、まるで意識にのぼっていなくて。
不安だった。
怖かった。
あなたに背を向けられても、私はここに居て闘うことができるのか自信がなかった。
あなたの指先が、私の頬を撫でる。目元をそっと拭う。
やっぱり見つかってしまった。
こういうのは目聡いひとだから。
「・・・妬いてくれたんだ?」
あなたはずるい。
甘い声で、そんな事を言うなんて。
私はただ、頷くことしかできなかった。