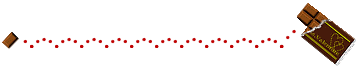|
(3)
人の波が続いている。
途中でうねっているものの、整然と並んでいるのは見事というしかない。
スリーはこういうのは暗黙の了解と言うのだろうかと感慨深かった。
誰が統制をとっているのでもない。が、横入りする者とて無く、みんなきっちり真面目に列を作っているのである。
こういう場所は初めてのスリーは、全てが物珍しくきょろきょろしていた。
女性ばかり。
当たり前といえば当たり前である。何しろバレンタインデーなのだから。
この日に開催されるイベントの主役はやはり女性だろう。誰もが手に手にチョコレートと思しきものを持っているし、いわゆる「本命」らしくプレゼントも添えて。
――プレゼントまで考えてなかったわ。
スリーはチョコレートしか用意していなかったので、少しだけそれを悔やんだ。とはいえ、このあとデートするのだし、一緒に居ることが自分にとっては大事なことだしおそらく彼もそうだろう・・・と思いかけ、やあね私ったらと頬を赤らめた。
ハリケーン・ジョーとデート。
そんなこと、今この場でうっかり言おうもんならどんなことになるか。
スリーは改めて気を引き締めた。
そう、今日は特別な日なのだから。
ハリケーン・ジョーのファンクラブなるものがあると知ったのは、いつぞやのグランプリであった。
初めて行ったサーキット。ピット。パドック。それぞれのパイロットの「応援席チケット」などというものがあるのも知らなかったし、そういうチケットがファンクラブに優先的に回されるというのも知らなかった。
だから、知った時は驚いたし嬉しくもあったので――こっそり手続きをすませてしまったのである。
もちろん、ナインは知らない。
――その「ファンの集い」に行くだけだもの、構わないわよね?
だって私は「ハリケーン・ジョー」のファンだもの。
そんなわけで、今、スリーは「ハリケーン・ジョーのファンの集い」なるものの会場に来ているのであった。
手にはチョコレートをしっかり握り締めて。
並んでいるのは「握手」をするための長い長い列であった。
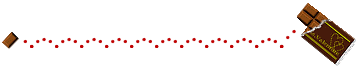
きっかけはほんの悪戯心だった。
バレンタインデーに会えないのは、仕事が入っているせい。だったらその場に行ってしまえばいいじゃない。と。
例えばこれが、行くことによって彼の邪魔になったり迷惑になるようなものだったら絶対にしない。が、「ファン」であり、彼の仕事の「対象」であるならば何も問題はないはずである。
むしろ「ファン」である自分が現地にいないほうがおかしい。
レーサーとしての彼に対してもアコガレに似たような気持ちを抱いていたから、スリーは彼のそんな姿を見るのもとても楽しみだった。
ちょうどバレンタインなのだから、自分も彼の素敵な姿を見れるのは嬉しくて幸せだし、ちょうどいいと思った。
そして、自分と相対した時、彼はどんな顔をするのか、想像するのも楽しかった。
だから、そう――ほんの悪戯心、でも根元にはしっかり恋心が在ったのである。
楽しみでわくわくして浮かれていたから、スリーは以前ナインが言っていたことをすっかり忘れていた。
ファンの集いなるものがどういうイベントなのかということを。

気付いたのは、列がずいぶん進んでからだった。
それまでは、周囲をきょろきょろするのに忙しかったし、見るもの全てが初めてで楽しかったし、それにナインがどういう顔をするのか、どんな反応をするのか、想像するのに忙しかったのだ。
だから、しばらくしてそれらが自分のなかで消化され落ち着いた頃、やっと周りが目に入ったのである。
もうすぐだわ、あと・・・50人くらいかしら。
そんな感じで前方に目を遣り――ナインの姿が見えてきて。
仕事をしているナインを見てドキドキしたりして、何て言おうかしら何て言うかしらと思っていた時だった。
「・・・えっ?」
――なに、あれ。
小さく心のなかで言ったはずなのに、声に出ていたらしい。賑やかすぎる屋内だったけれど、そばにいた女の子にはしっかり聞こえていたらしい。
「あの、もしかして初めてですか?」
「えっ?ええ・・・」
髪をくるくるカールした可愛い女の子だった。
「ハリケーンジョーのファンの集いっていつもあんな感じなんですよ」
「・・・あんな感じ・・・?」
「最初は照れちゃうけど、でもレースでいろんな国に行ってる国際的なひとだから、こういうのもありかなってだんだん普通になってくるのよ」
「普通に?」
「だって、ほっぺにキスするくらい挨拶と同じでしょう?私たち日本人は慣れてないけど・・・あなたは大丈夫でしょう?」
蒼い瞳。どこからどう見ても外国人であるスリー。
「日本語が上手なのね。ね、どこでハリケーンジョーを知ったの?どこかの国?」
「・・・いいえ、日本です」
「じゃあ日本に住んでいるのね」
「ええ」
「日本グランプリとか行ったことある?」
「ええ」
「私も!じゃあ、どこかですれ違っていたかもしれないわね。――素敵よねぇ。ジョーって」
ジョー。
他の女の子が彼の名を呼ぶのを聞くのは、複雑な気分だった。
もちろん、ミッションでは誰もが彼をそう呼ぶけれど、「ナイン」のほうがそれでも圧倒的に多かったのだ。
|