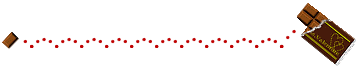|
(5)
「――こんにちは」
にこやかに言うハリケーン・ジョー。
「こ、・・・こんにち、は」
ナインの第一声とその視線にスリーはうちのめされた。
何故なら彼は、驚きもしなかったし怒りもしない、もちろん笑いもしなかったのだ。
一瞬の変化も見られない。表情にも声にも物腰にも。
スリーに向けられる全てが、ここにいる誰しもに向けられるものと同じだった。
「今日は来てくれてありがとう」
「い、いいえ。・・・あの、これ」
握り締めていたチョコレートの入った箱を渡す。
「うわあ、嬉しいな。ありがとう」
ハリケーン・ジョーは優しく笑むとスリーの両肩にそっと手をかけて頬を合わせた。
「本当にありがとう」
「・・・いいえ」
小さく言って、スリーは身を引いた。
握手もサインも求めない。
最初はそのつもりだったのに、今となってはそんなものどうでも良かった。
「・・・」
黙ったままのスリーにハリケーン・ジョーは何かを待つようだったけれど、待っても何も言わないので
「今日は本当にありがとう」
もう一回言った。
そして、それが「いちファン」であるスリーとの短い邂逅の終わった合図だった。
 

――フランソワーズのバカ。
逃げるようにその場を去り、かといって建物から出てしまうわけにもいかず――いちおう「迎えに行くわね」と言った手前、待っていないわけにはいかないのだ。そのへんスリーは律儀であった――トイレの個室でひとりスリーは涙に暮れていた。
いまのジョーはハリケーン・ジョーなんだもの。私の知らないひとなんだもの。
みんなと同じようにされるの、当たり前でしょう?
なのにそれが不満で、それが寂しいってどういうこと?こんなの、ただのワガママなオコサマじゃない。
ハリケーン・ジョーは完璧だった。
スリーと既知であるとは毛筋ほども態度に出さなかった。
ちょっとは驚いてくれるとか、どうしたんだい、って笑ったり、何でここにいるんだ、って怒ってくれるとばかり思って期待していた自分が、いかに甘かったのか痛感した。
そして後悔した。
――来るんじゃなかった。
ハリケーン・ジョーに会ったりするんじゃなかった。
チョコレートだって、スリーは「ナイン」もしくは「ジョー」に渡すつもりで作ったのであって決して「ハリケーン・ジョー」に渡すためではない。
なのに渡してしまった。
きっとダンボール箱に詰められ、どこぞに贈られてしまうのだろう。手紙も何もつけてないから、大量のそのなかからスリーのチョコレートを見つけだすなど無理な話だった。
私ったら、なにやってるんだろう?
今日は楽しくて幸せな日になるはずだったのに。
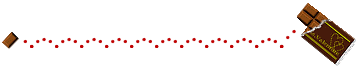
どのくらいそうしていただろうか。
いい加減、トイレの個室にこもっているのも飽きてきた頃、携帯電話が振動した。
見ると、ナインからのメールだった。
『いまどこにいる?』
スリーは涙を拭うと個室から出た。
鏡に映る自分の顔は、酷いものだった。とても好きなひとに見せられるようなものではない。特に、先刻まで可愛い女の子たちに囲まれていたひとには。
後悔と反省と少しばかりのヤキモチと、特別扱いされたいワガママな思いが混じり合った気持ちが顔に表れていて、スリーはため息をついた。
こんな顔を見せたら、何があったのか全部言うまで許してくれないだろう。
バッグから化粧ポーチを取り出して、とりあえずリップだけ塗りなおした。あとはどうしようもない。
再び携帯電話が振動した。
今度はメールではなく通話だった。返信してこないスリーにしびれを切らしたのだろう。
スリーはのろのろと耳にあてた。
「――ジョー?」
「フランソワーズ!さっきメールしたんだけど見なかったのかい?いまどこにいる?」
「どこ、って」
「いま終わっていつでも出れるからさ」
「・・・そう」
「フランソワーズ?何かあったのか」
「ううん。何もないわ」
そう――何も。
「フランソワーズ。いま居る場所を言って」
「えっ?」
「そこに行くから」
「でも」
「いいから。僕が行くまでそこで待ってろ。いったいどこにいる?」
スリーは現在地を伝えた。
「そうか。わかった」
ナインは短く言うと通話を切った。
そうして約3分後には女子トイレの前に到達していた。
|