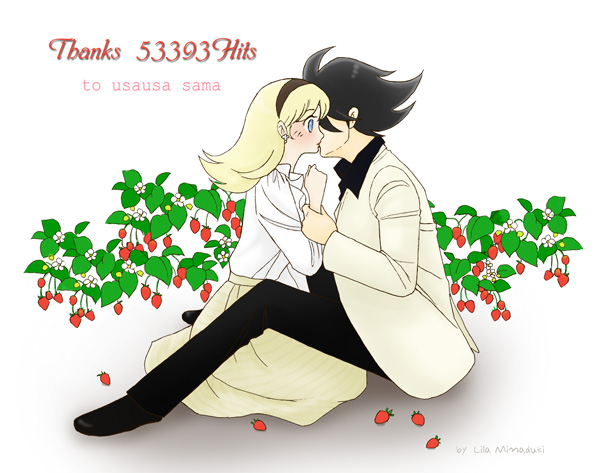|
「すごーい。たくさんのイチゴ!」 ビニールハウスの入り口で胸にいっぱいイチゴの香りを吸い込み、スリーは中へと一歩踏み出した。 「いいにおい・・・。ね、ジョー。こんなにたくさんあったら、ケーキもタルトも何でも作れるわね」 ナインはスリーの後ろから続いて中へ入った。 「またそう言う。ひどいわ、ジョー」 私はオコサマじゃありません――と、横を向くスリーの手をとり、ナインは微笑んだ。 「ホラ。そういうトコロがオコサマなんだよ」
「おーい。早く中に進んでくれよ。後がつかえてるんだから」 背後から声がかかり、ナインとスリーは慌ててビニールハウスの中ほどまで進んだ。 「もうっ。ジョーが変なコト言うからよ?」 スリーが横目でナインを見て唇を尖らせる。 「だってさ。ケーキとかタルトとか言うから」 スリーは右手でそっと傍らのイチゴをつついた。左手はナインとつないだままである。 「ケーキとかタルトもいいけどさ。そのまま食べる方が美味しいんだぞ。特にこういう所ではね」 そう言うと、ナインはイチゴをもぎとり、ぽいっと口に放り込んだ。 「ウン。うまい」 スリーも真似してイチゴをもぐ――が、片手だけでは上手くできなかったので、ナインの手を離そうとした。 「ジョー、ちょっと・・・」 手を離して、と言いかけると、目の前にもぎたてのイチゴが出現した。 「ホラ」 ナインが差し出すそのまま小さくかじってみる。 「――ホント。甘くておいしいっ」 二人は手をつないだまま、ぶらぶらと奥のほうへ向かって歩いてゆく。 「凄いなぁ・・・広い」 ビニールハウスとはいっても、小学校の体育館くらいの広さがある。そこへ縦に幾筋もイチゴが連なって植えられている。入り口寄りには腰の高さに組んであり、屈まなくてもイチゴを摘むことができる。真ん中より奥の方は、砂の上のシートにイチゴが並んでおり、こちらはしゃがまないと採れない。品種が異なっているようだった。が、ナインとスリーの二人はそんなことは知らない。全く頓着せず、手を繋いで歩いてゆく。 「ここで食べるのも美味しいけど・・・、でも、後でケーキも作るわね?」 「一緒に来ればよかったわ」 何故かセブンは博士の学会に同行しているのだった。 「・・・そうだけど」 ナインはスリーを見つめ、優しく微笑んだ。 「だったら、たくさん採って帰らないと」 そうして二人はしゃがみこんで、しばらくイチゴの収穫に精を出していたのだけれど。 「あ、ジョー。もうっ。あなたったら、採るより食べる方ばっかり」 ナインの手元のイチゴは、スリーより随分少なかった。 「ん?そりゃ、このために来たのにさ。食わなくてどうする。――ホラ、きみも一つ食べたまえ」 そうしてスリーの口元にイチゴを近づける。 「ん。後にするわ」 美味しいのになあ――とナインは呟きながら、そのイチゴもぱくりと食べてしまう。 「知ってるかい?イチゴってヘタの方から食べた方が美味いんだぞ」 スリーの蒼い瞳が丸くなる。 「ウン。甘みを感じるのが舌の先だから、イチゴの一番赤いところがそこにくるように食べるのさ」 「えっと、こうかしら?」 スリーの手からイチゴを取り上げ、ヘタの部分を取る。 「そうして、ヘタの方から・・・」 ナインからイチゴを受け取り、口元へ持っていく。ナインはその仕草を目で追いかける。 「・・・ジョー?どうかした?」 スリーがイチゴを食べる直前に手を止め、訝しそうにナインを見つめる。 「ウン・・・そのイチゴの赤い色が、きみの唇の色と同じだなあと思ってさ」 甘そうだ。 スリーは至近距離に近付いたナインを見つめ、不意に落ち着かない気分になった。急に心臓が暴れ出す。 「あ、あのジョー?どどうしたの」 甘そうだから。 「や、ジョー、ちょっと・・・きゃっ」 近付くナインを避けるように身を退いたスリーはバランスを崩し、そのまましりもちをついた。 「何やってるんだよ。バカだなあ」 ナインは笑いながら、スリーの腕を掴んで助け起こした。 「気をつけろよ」 スリーを助け起こすのに手を強く引きすぎて、ナインはスリーを起こした途端、今度は自分が仰向けにしりもちをついていた。当然、ナインに手を引かれたままのスリーも一緒に。 「きゃっ」 ナインの身体の上に散らばるイチゴ。 「やだもう、ジョーってば・・・」 ナインはスリーの腕を掴んだまま引き寄せ――そうっと唇を重ねていた。 周りに広がるイチゴの香り。 唇に残るイチゴの甘さ。――と、コンデンスミルクの甘い味。 「・・・・・・・」 ナインは内心、がっくりと肩を落とした。 スリーとの初めてのキスだったのに。なのにどうして、彼女の香りではなく、コンデンスミルクの味なんだ。 「・・・ジョー。・・・こんな所で・・・」 スリーは顔を真っ赤にしてナインから飛び退いた。ばらばらに落ちたイチゴを慌てて拾う。 ――でも、彼女の唇は凄く柔らかくて・・・ 「もうっ。ジョーのせいでイチゴがバラバラ」 軽く唇を尖らせ、ナインを見ないようにしながら手元のイチゴを拾い集める。 「ねえ、ジョーも手伝って」 呼ばれてもスリーはナインの方を見ない。耳まで赤くしたまま、イチゴを拾うことだけに集中している。 「・・・何?ジョー」 スリーが答えるのを待たず、ナインは優しく唇を重ねていた。 何か言ったようだったけれど、聞こえない。 スリーの手からイチゴがころんと転がった。
|