|
僕がスリーのレッスンの送り迎えをしているのには理由がある。
それは、決して色っぽいものではない。
あくまでも任務なのだ。
何故なら、一度彼女は拐われそうになったのである。
その時、僕はそこにいなかったけれど、たまたまセブンが一緒にいて事なきを得た。
後になって聞いて、冗談ではなく血の気が引いた。
無事だったからよかったものの、万が一ということもある。
スリーはけろりとしていたけれど、僕はその時固く心に決めたのだ。
きみのことは僕が守る。と。
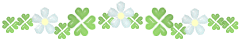
たぶん送迎を始めてから5回目か6回目だったと思う。
僕のなかでは送迎は当たり前の事になっており、日常のルーチンワークとなっていた。
だから、その日もいつもと同じように言った。
「じゃあ、いつもの時間に来るから」
「えっ?ええ・・・」
なんだかぎこちない笑みを浮かべるスリー。
「どうかした?何か用事でもあるのかい?だったら」
「ううん、そうじゃないの。いつもの時間で大丈夫よ」
「そう。じゃ」
「待って、あの」
その日はスリーはなかなか車を降りなかった。
「何?」
「あの、・・・もう大丈夫だから、その」
「大丈夫って何が」
「もう、ひとりで帰れるわ、だから」
僕は無言でスリーを見た。スリーは僕の視線を避けるように下を向く。
・・・まったく。
いったい何を遠慮しているんだか。
「スリー。僕のガードじゃ安心できない?」
「ち、違うわっ、そうじゃなくて!」
跳ねるように上がった顔。頬が赤い。
「そんなこと思ってないわ!ただ、ナインに付き合ってもらうの、悪いなって思って、・・・だから」
「・・・スリー」
僕は溜め息をついた。
何を遠慮しているのか知らないけれど、送迎をやめるなんて冗談じゃない。
「勘違いしてもらっては困る。これは任務だ」
「任務・・・」
「ああ。だから、変に気を回す必要はない」
「・・・そう、ね」
スリーは少し冷静になったのか静かに頷いた。頬の赤みも退いている。
「そう・・・よね、・・・任務、よね」
「そうだ」
スリーは小さく、わかったわと言うと車を降りた。
そのまま振り返りもせず小走りに行ってしまう。
・・・あれ?
いつもなら見送ってくれるのに。
後でね、って可愛く笑って手を振るのに。
今日は急いでいたのだろうか。
僕は車を発進させながら、遠ざかるスリーの姿をバックミラーで確認した。
任務、か。
確かにそれは事実だったけれど。
だけどそれを口実として大いに利用しているということは僕だけの秘密だ。
公然とスリーを独り占めできる時間を手放すわけがない。
僕の大事な女の子。
きみはそれくらいわかっているよね。
敢えて口にしなくても。
旧ゼロトップはこちら
|