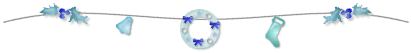
目が覚めたら、腕の中にフランソワーズがいた。
既に起きていて、僕に気付くと恥ずかしそうに微笑んだ。
「・・・おはよう、ジョー」
「おはよう、フランソワーズ」
うっすらと陽が射している部屋。
暖房は消してあるけれど寒くない。
腕の中の柔らかい存在が僕に温かさを与えてくれる。体と――心に。
どうしてだろう。
こうして抱き締めて迎える朝はいつもより嬉しくて幸せで・・・泣きたくなる。
「ジョー?どうしたの」
「えっ・・・別に、なんでもないよ」
「そう?」
フランソワーズはくすりと小さく笑った。
僕は自分の気持ちが見透かされたようで落ち着かなくなったから、彼女の体をぎゅうっと抱き締めた。
夜ではなく朝にこうしてきつく抱き締めて素肌を合わせると、以前は驚いたように体を固くしたものだったが
今ではそんなことはなくて、僕の思うようにさせてくれる。
いや、むしろ――甘えるように身を寄せてくるのはフランソワーズのほうだろうか。
昨夜の僕はいつもの僕のままだったろうか。
ふと気になった。
フランソワーズがどう思ってくれているのか昨夜聞いたけれど、それでも――不安は完全には消えなかった。
「――フランソワーズ」
「なあに?」
「その・・・昨夜だけど」
「ん?」
「いや、その」
何て言えばいいのだろう?
昨夜の僕は変じゃなかったかい?――だろうか。
でも、何をもって「変」であると定義するのだろう。人間なんてどこかしらみんな変なのに。
昨夜の僕は、・・・きみに夢中になりすぎていなかっただろうか?
うん。これだ。
いくら夢中になってくれるのが嬉しいと言ってくれても、それに甘えてはいられない。
気を遣って言ってくれただけで本心ではないだろうとは思わないけれど、それでも・・・僕はきみを傷つけたくない。
だからもしも、きみが何か困ったのだったらそう言って欲しかった。
しかし、僕が次の言葉を繰り出す前にフランソワーズが先に言葉を紡いだ。
「ねぇ、ジョー。私、考えていたんだけど」
「なに?」
やはり――昨夜、僕は何かやらかしたのだろうか。
心理的に身構えて彼女の言葉を待った。
「ん・・・あのね。私ももうちょっとあなたに夢中になったほうがいいのかしら、・・・って」
「え!?」
「やだもう、こっち見ないで。・・・だから、ジョーが夢中になってくれるのと同じくらい、私も、って」
ええと、それっていったいどういう・・・
「でも、どうすればいいのかわからないから、・・・教えてくれる?ジョー」
「教える、って・・・」
「だって、どうすれば気持ちがちゃんと伝わるのか、わからない・・・から」
頬を真っ赤に染めて困ったように訴えるフランソワーズ。
僕は思わず笑ってしまった。
まったく、何を言い出すのかと思ったら。
けれど、彼女のその言葉で僕のなかにあった不安な気持ちは綺麗に消えてしまった。
「もうっ、笑わないで、私は真剣なのよ?」
ねぇ、フランソワーズ。
僕はいつでも君だけを見ているよ。
もしも、君が僕を見なくなってもそれでも――
アイシテル
誰よりも、君だけを
