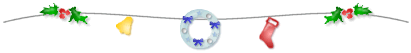
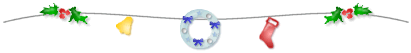
「フランソワーズ、クリスマスはどうするの」
期末テストも終わり、後は冬休みまでの消化のような時間割。
そんなのんびりした雰囲気に浸ってぼうっと窓の外を眺めていたら、クラスメイトのカトリーヌとヒルダがやって来た。
「どう、って…?」
何が?と首を傾げると、二人ともああもうこれだからと揃ってため息をついた。
「――まあ、どうせ島村と過ごすんでしょ」
「え。過ごさないよ。それはそっちのセリフでしょ」
カトリーヌはフィリップとらぶらぶだし、ヒルダはハインリヒとアツアツだし。
「またまたあ。ウチらに隠さなくたって大丈夫だって」
「そうそう。ちゃんと知ってるから」
島村とフランソワーズが恋人同士っていうの、秘密なんでしょ?
二人が内緒話のように顔を寄せて囁く。
「恋人かあ…」
私はため息とともにその甘やかな響きを吐き出す。
「――そうなのかな?」
「え、フランソワーズ何言って」
「嘘、まさか」
別れたの?
小声で、でも綺麗にユニゾンで言ってのけた二人。
「ん…別れるも何もそもそも付き合っているのかどうかわからないし」
「何ソレ」
「島村ぁ、アイツ何やらかしたんだあ?」
「何もやらかしてない」
「じゃあ、フランソワーズが何かやらかしたの?」
「ううん。何にもしてない」
「もー。意味がわからないんですけど」
困った顔の二人に、私は薄く笑みを作った。
「彼には予定があって、私はそれに組み込まれていない。というだけ」
「予定?」
「バイトとか?」
彼が苦学生なのは有名であった。
「ううん。バイトじゃなくて――何か、女の子と予定があるみたいよ?」
「えっ」
「嘘っ」
残念ながら本当だ。
だって本人から聞いたのだから。今朝。
「だから、私のクリスマスの予定は――お兄ちゃんと過ごす感じかな?」

今朝。
珍しく登校していたジョーにクリスマスはどうするのと無邪気に訊いた。
何の懸念もなく。彼から、そうだねどうしたい?なあんて聞き返してくれるものだとばかり考えて。
だから、何の心理的防御姿勢もとっていなかった。
そんな無防備な私の心に彼は。
「クリスマス?別にどうもしない――あ。ひとと会う予定があったな確か」
そんな思わせぶりなセリフで斬り込んできたのだった。
「――ひとと会う?予定?それって」
女子?
ううん、男子?
いやでもクリスマスだよ?男子同士ってことはないよね。
でもまさか女子…なわけ、ないじゃない。だって私とジョーは恋び
「女の子だけど何か?」
――恋人同士、って思っていたのは私だけだったのか…な?
そうだよね。
たぶん。
私ひとりがそう勝手に思っていただけで、ジョーから見ればたくさんいる彼を好きな女の子のなかのひとりに過ぎなくて
ああでも待って。私がジョーを好きだなんて彼は知るわけないか。だって言ってないし。
――言ってないよね?
いや、言ったっけ…?
混乱してる。
私は「女の子だけど」と言った時の、ジョーのちょっと照れくさそうな頬の緩み方に成す術もなかった。
だって、そんな顔。私、見たことない。
そんな――まるで、大事なものを思い浮かべて頬が緩みそうになるのをちょっと我慢しているみたいな。そんな笑い方。
どれだけその子を好きなの?って思うくらい。
ジョーにそんな顔をさせる見知らぬ子にその瞬間激しい嫉妬をした。真っ黒に塗り潰されてゆく心。
「んーん。何でもない」
だってそう言うしかないじゃない。
「あっそ」
ジョーは小さくそう言ったあと、興味なさそうに教室を出て行った。
だってそう言うしかなかったじゃない。
だって――フランソワーズはどうするの?って訊いてはくれなかったのだから。
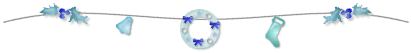
「それはイメージじゃない」
「じゃあこれは?」
「大人っぽすぎ。てかケバい」
「うーん。じゃあ、これ。可愛いわよお?」
「あのさあ。高校生なんだよ。そんなの、子供っぽすぎるだろ」
「まー、生意気。高校生なんてまだ子供じゃない」
「子供だけど、もっと大人びた感じなんだよ彼女は」
「ふうん…」
「…なんだよ」
「べっつにぃ」
「ちょ、勝手に腕組むなよ」
「いいじゃない、減るもんじゃないし」
「ったく、ユリさんは…」
クリスマスカラーに色づいた街。腕を絡めてくる年上の彼女を持て余しながら歩く。
頭の中は、最前から他の女性のことでいっぱいだ。
――っていうか、彼女のことしか考えてないわよねえ。
まったくもう。
苦笑しつつ見上げる彼の横顔は、嬉しそうな照れくさそうな。
こんな顔させる彼女っていったいどんな子なのよ?
「――ねえ、ジョー?」
「ん?」
「いいの?私とこんな風に歩いてて」
「って何が?」
「彼女が見たら誤解するんじゃない?」
「は?」
きょとんとしてこちらを見たジョーにユリは内心頭を抱えた。
なんなの、もう…っ
無防備すぎる。
心配する余地もないくらい彼女が好きで、そして彼女から好かれていることに自信を持っている。
だったら。
「あのね、ジョー。だったら彼女と一緒に選べばいいじゃない。プレゼント。好きなのわかるし外さないわ」
「駄目だよ、そんなの」
「なぜ?」
「なぜ、って…それは」
ごにょごにょと呟いたジョーの言葉にユリは大笑いした。
まったくもう。
いつの間にそんな可愛いことを言うようになったの?
荒れていた中学時代を知っているから、彼が今する表情や口にする言葉はどれも新鮮だったし、そうできる彼に安心して
ちょっと涙ぐんでしまったことは内緒だった。
でもね。ジョー。あなたはひとつ間違っている。
可愛く『彼女の驚いた顔が見れないじゃないか』なんて言ってもこれじゃあ全然通じないんだよ?
「だったら、いいこと教えてあげる」
***
私は他の人より目がいい。
というか
目聡い――らしい。どうやら。
――だけど。
フランソワーズは深いため息をついた。
こんなの、見つけなくたっていいのに。
視線のずーっとずーっと先の、豆粒ほどの雑踏の中に。
知らない女性と腕を組んで歩いているジョーを見つけてしまった。
長い黒髪。細身の身体。そして何より。
ジョーと笑い合ってじゃれあっている。
「ふうん…」
そういうこと。
なんだ。年上の彼女がいるなんて知らなかったよ。
あるいは、もてるジョーのことだから、年下の彼女もいるのかもしれない。年上、同世代、年下に各ひとりずつ。
そういえばずっと前――マユミという女性ともめているのを見たこともある。
――私はひとすじなんだけどなあ。
視界が滲んだので空を見る。
確かに「他に彼女がいるの?」と訊いたこともなければ「何人彼女がいるの?」と訊いたこともない。
が、「他に好きなひとはいないよ」と言われたこともないし「フランソワーズだけしかいないよ」とも言われていない。
「なーんだ。私」
――何番目なんだろう。彼のなかで。
そう思うのは物凄い屈辱だったし、それ以上に辛く悲しかった。
けれど、彼のなかで自分の順位は低いのだと思い知ったのだった。