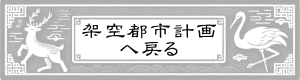|
||||||
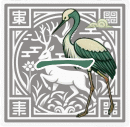 キーパー:『鵷鶵文書』の中に翡翠製と思われる香炉があって、「これは何か調べようがあるかもしれない」と話題になっています。両手で持てるくらいの、でも仏壇に置くには大きすぎるサイズ感です。結構凝った彫刻が施されていて、下の炉の部分には膝を折って座る鹿が、蓋には1羽の鶴が彫り込まれています。素人目にも「中国っぽいな」という印象を強く受けます。香炉には使用された形跡はなく、桐箱に収められた状態で行李の中に入っていました。桐箱の蓋の裏書には「伝 陽勝香炉」と書かれています。 村雨:「“陽勝香炉”として伝わっていますよってことですよね?」 泰野教授:「そうね」 キーパー:調べると簡単に分かるので説明しますと、“陽勝”っていうのは、実在したとされる平安時代中期の天台宗のお坊さんです。 陽勝は比叡山で修行後、金峯山と吉野の牟田寺で山林修行を行なって仙術を身に着け、“陽勝仙人”と呼ばれるようになりました。彼は全身に長毛を生やし、翼を使って空を飛んだ、あるいは翼なしでも飛行できたと伝えられています。ある夜、かつての師僧、増命のもとを訪れ、昔話をした後、長く“人気(じんき)”に当たり飛べなくなりましたが、香炉から立ち昇る煙に乗って再び空へ帰っていったというエピソードが『今昔物語』にあります。 宇乃:その話に出て来る香炉が“陽勝香炉”って呼ばれているってこと? 宇乃:その話に出て来る香炉が“陽勝香炉”って呼ばれているってこと?キーパー:いいえ。陽勝と香炉に関する話は伝わっていますが、別に“陽勝香炉”っていうアイテムがあるわけではありません。話に登場する香炉が翡翠製であるという話も伝わっていません。 宇乃:香炉がいつの時代に作られたものかっていう手がかりはありませんか? キーパー:様式などから調べれば、判明するかもしれません。 村雨:増命と陽勝の話は平安中期っていうから、もしかしたらそのあたりかもしれませんね。 佐山:じゃあ、もしかしたら増命の話に出てきた香炉が、この香炉という可能性もありますね。 宇乃:それなら中国様式だっていうのも納得できる。この時代の翡翠の香炉ということは、例えば考古学的に価値のあるものという認識で間違いないですか? キーパー:それは〈考古学〉か、〈芸術/製作〉ロールをしていただければ。金銭的な価値なら〈鑑定〉です(※村雨が〈考古学〉で成功)。どうやら香炉は平安時代よりも古いもののようなので、それなりに価値のあるものです。 佐山:平安よりも前で高い技術で作られているとなると、やはり中国製である可能性が高いですね。 キーパー:中国の時代でいうと、どんなに新しく見積っても唐代という話になってきます。 宇乃:最澄が持って帰ってきた香炉の内の1つと考えられるかもしれない! キーパー:下手するともっと古い可能性もあります。 宇乃:膝を折った鹿とか、鶴とかのモチーフで何かピンとくることはないですかね? キーパー:それなら……〈歴史〉、〈オカルト〉、〈人類学〉、あとは単純に〈知識〉でも良いので、ロールしてみてください(山田以外成功)。成功した方は分かりますが、鹿も鶴も長寿、もしくは不老不死を象徴するものとして、主に中国で崇められていますね。 泰野教授:なるほど。とりあえず、何かいろいろと調べられる取っ掛りはある感じよね。
|
||||||