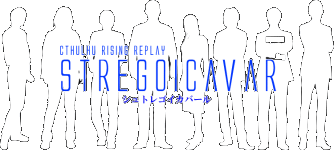
キーパーの言い訳。ここ数年のミッション失敗の連続を立て直すべく、ドラスティックに設定を変えようと思い立ち、ついカッとなって訳した『Cthulhu Rising』。当初はWeb公開されていた導入用シナリオを使ってみようと思っていましたが、どう考えても導入用とするには複雑すぎる内容。これではまたしてもミッション失敗となりかねないと判断して、急きょ新規に作ったのがこのシナリオです。完成してみたら、あまりSFクトゥルフでやる必要もない内容になってしまいましたが、個人的には宿願であった“黒の碑”をテーマにできて満足しています。 『Cthulhu Rising』自体、半同人的作品なのでルール周りに多少使い辛さがあるため、終末同盟版として若干簡略化して運用しました。<リーダー>とか<教授>等の説明の欠けた重要度の低い技能は削除し、<捜索>技能は伝統的な<目星>で吸収、<尋問>や<雄弁>は<説得>技能に一本化、等々。これでもSFRPGらしい<コンピュータ>技能や<エレクトロニクス>技能の細分化によって技能数がかなり増えています。部位耐久力採用による命中部位判定や、部位ごとの装甲値、負傷時の効果ルール、戦闘オプションの追加により、戦闘処理はかなり重くなるはずです。このあたりも戦闘行為が致命的な『トラベラー』を意識しているのがうかがえます。今回のプレイでは(例によって)戦闘は適当に処理しましたが、厳密な運用にはキーパーとプレイヤーの両方にかなり詳細な理解が必要と思われます。 政治や経済を巨大組織(統一地球連邦や12大企業)にまとめて単純化しているので、シナリオへの導入には頭を悩ませなくても良いのかもしれません。これも『トラベラー』っぽく政府や企業からの依頼という形が繰り返し使えそうです。逆に「山間の小村で25年に一度行われる奇祭の裏に隠された宇宙的恐怖」という、湿った伝奇ホラーにSFは向かない気もします。『エイリアン』シリーズの雰囲気がしっくりとくるのかもしれません。 今回のシナリオは、真相は探索者の手の届かないところにある「体験型」のシナリオです。事件は探索者の行動を上回る速度で展開していき、神話的恐怖をたっぷりと体験した後、最終的に命からがら逃げだすというものでした。結局、R-38Y研究所内で起こったことはほとんど明かされず、ポルンガ博士のモチベーションなども不明のままです。しかし探索者は大量の正気度を失いながらもミッション(サマセット博士の救出)をなし遂げた上で生還しているので、100点満点をあげられると思います。 素材提供サイト バックグラウンドタンク様(背景) シェルの素材工場様(ボタン) ジュエルセイバーFREE(キャラクター・イラスト) ←私のような絵の描けない人間にとっては夢のコンテンツ! |