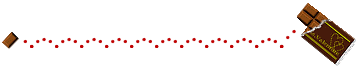|
―5―
数分後。 「コーヒーでも淹れるわね」とリビングを去ったスリーを待つ間、ナインはここしばらく感じていなかった、心が温かくなってゆく感覚に身を浸していた。やっぱり自分は、彼女がいないとダメだ。彼女じゃないと――ダメだ。 「お待たせ」 キッチンから戻ってきた彼女は、コーヒーだけではなく他のものも一緒に持って来ていた。 「・・・はい。ジョー」 ブルーのリボンがかかった小さな箱。 「えっ・・・なに?」 チョコレートか。 隣で自分を見つめているスリーを気にしながら、ゆっくり箱を開けてみる。そこにはひとくち大の小さなハート型のチョコレートが詰まっていた。 「・・・ありがとう」 カードも何もついてなくて。もちろん、プレゼントなども添えられてはいない――けれど。 「・・・あのね。ジョー」 繋ぐともなく繋いだ手元に視線を落とし、ゆっくりとスリーが言う。 「私、思ったんだけど、・・・確かジョーにまだ言ってなかったわよね?」 何を?とは訊かない。 「言わなくてもいいかなって思っていたの。だって、ジョーはとっくにそんなの知ってるよって顔をしてたし。・・・だから」 そう。 「・・・好き」 しかし、ナインは微笑むと繋いでないほうの手を持ち上げ、指先でスリーの唇を封じた。 「言わなくてもいいよ」 スリーもにっこり微笑むと彼の指をそっと除けた。 「だけど、知ってる?今日はそれを言う日なのよ」 「私はジョーが」 言う事をきこうとしないスリーを持て余し――ナインはそのまま彼女の唇を唇で塞いだ。そうして少し考えて―― 「・・・・っ!」 繋いだスリーの指に力がこもる。 そもそもの発端は、このキスだったんだよなあ・・・と思いながら。
イチゴ狩りに行ったあの日。 イチゴ畑で初めてスリーとキスをした。 帰りの車の中でもお互いに楽しく話した。 三度目はちょっと違った。 ナインとしては、昼間のイチゴ畑のキスでじゅうぶんに満足していた。――つもりだった。 だから。 三度目のキスは、恋人同士のキスになった。 驚いて、ナインから離れようとしたスリー。 それからだった。
今思えば、彼女はそういったことの知識はあっても、慣れてはいないんだから、もう少しゆっくりでも良かったのかもしれない。同じ日にキスのステップアップをしなくても良かったのかもしれない。だけど。
いま、二度目の「ちゃんとしたキス」を受けるスリーは、前回よりも平静な自分に驚いていた。 前回は、突然のことにどうしたらいいのかわからなかったし、何より未知の世界へ導くナインがとても怖かったのだ。 彼とそうなるなら、怖くないわという結論に達するまで、ずいぶん時間がかかってしまった。 いったい自分はどうしたいのか、考えて考えて、そして。 ナインとそういうキスをしても嫌ではなかった という事実。 でも。 ナインの目を見たらわかった。
そんなキスの後、ナインはスリーの両頬にそれぞれ唇をつけた。 「・・・特別だからなっ。ふだんはいっぺんに両方なんてしないんだぞっ」 そう言う顔は赤く染まっていた。
|